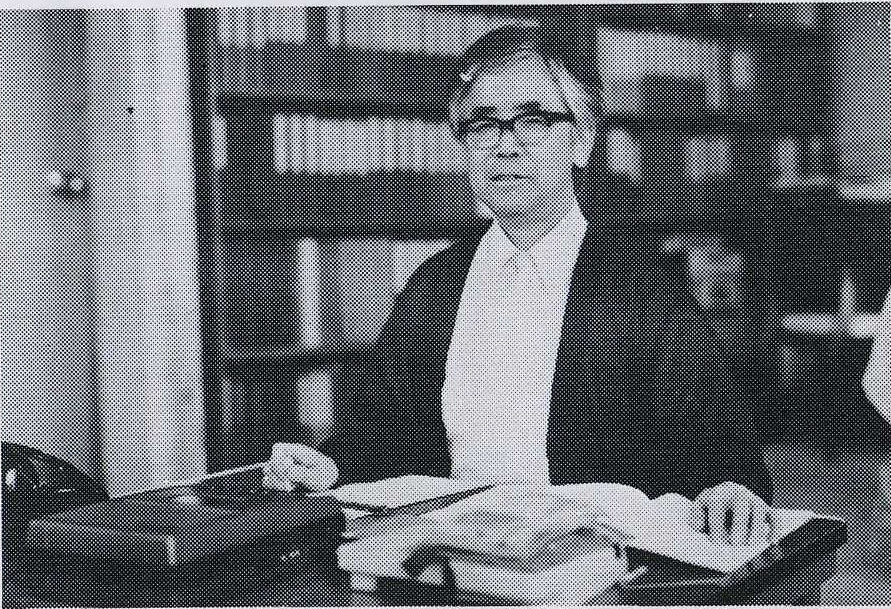4月
14
少国民と呼ばれたあのころ
写真(1)

昭和20年 14歳の春 秩父の生家にてハーモニカを吹く
表紙
日本禅書道学会会長 野呂雅峰 先生 書 (カット 大嶋昭彦)
ある日、一人の教師に、それは冗談まじりだったが、
「お前のような片輪の奴は、奴隷にもなれやしねえ。だからまず、みんな銃殺か毒殺だなあ、あるいは、しばり首かもしれねえ」
といわれた無神経なことばをふと思い出した。そのことばを思い浮かべたとき、私は自然に涙が流れるのをおぼえた。(本文抜粋)
私のすごした幼少年期・・・p1
p1
15年戦争時代の記憶
昭和20年(1945年)の8月15日、あのいまわしい昭和の歴史の一時期を、暗黒の歴史と化した、15年戦争が終結してから、昭和59年(1984年)8月15日がくると、早いもので39年になる。
世界中で世界の平和が祈られ、反核運動がもり上っている。こんな時期にアメリカのレーガン政権は、こともあろうに、一昨年(1982年)の広島原爆記念日の前日8月5日に、そうした反核運動に専念しつつある人びとの感情を逆なでするように、ネバタ州で地盤が沈下するほどの巨大なる原爆実験を、傍若無人にも行なっている。
それもつい何ヵ月か前に、アメリカのニューヨークで、国連主催の反核平和運動の世界大会が開かれたばかりだというのに、このような恐るべき無神経さで、原爆実験を行なっているのである。
p2
そしてその後もなお、いっこうにそうした実験をやめようとしないのである。これはまさに、人間の皮をかぶった悪魔の仕打ちとしかいわざるを得ない。
その後間もなく日本では、鈴木内閣が退陣、そして、刑事被告人でいながら、政界に悪唾の限りをとばしている、田中角榮の力を借りて誕生したといわれている中曽根内閣は、一般にいう行革法をはじめとする悪法をつぎつぎと国会に提案し、平和日本を軍国日本へと変貌させようとしている。
私はこうした現代社会の変遷を生きながらにして眺めているとき、ときどき私が幼少年時代に過したあの、15年戦争のいまわしい記憶を呼びさまされては、改めて平和日本の将来とか、世界の未来はどうなるのか、というようなことを、ある種の不安を心の奥に秘めながら考えることがある。
これから私が書こうとするものは、平和というものが如何に大切なことであるかということを、少年期に少国民として体験した生活をとおして、物語ろうとしているものである。
p3
◇
昭和6年(1931年)といえば、日本があのいまわしい昭和の歴史に消すことのできない、大きな傷あとを残した15年戦争の幕が切っておとされた、忘れられない年である。
その日本の軍国主義が、わがもの顔にのさばる素材を作った、不運な年に、埼玉県の奥地、秩父郡秩父町の本町に、『中村屋』という屋号で旅館を営んでいた両親の間に、私は五人兄弟の次男として生まれたのだった。
私の生まれた日は、そろそろ花便りもきかれようとしている3月、人の心もようやく春めいて何やら浮き立つような気分にさせられる時期であった。
その当時、日本の政府は急に発展してきた蒋介石の南京政府の行動に、おだやかならぬ干渉を加えていた。しかし中国統一運動は、そうした日本政府の執拗な干渉にも負けずに、次第にその力を蓄積しながら、徐々に満州地区にまで広がっていった。
昭和3年(1928年)に奉天(瀋陽)で起った張作霖暗殺のための列車爆破事件も、日本政府は満州に出没する、秘密ゲリラの仕業のように報道していたが、日本国軍の陰謀によるものであることは、すでに中国軍に知られていた。
p4
私の両親は男子出生ということで、大いに喜んだのであった。がしかし、その喜びの笑顔もすぐに消えてしまった。それは生まれた私が、身長も体重も当時の出生男児の平均値よりはるかに劣った、未熟児だったからである。
それでも両親は、せっかく生まれた男子ということで、大事に可愛がってくれた。特に母の献身的な努力が、私の生命をながらえさせてくれたのだと後で親戚のものから聞かされ、子どもながらに母に対して限りない感謝の念をもっていたのである。
その母の献身的な努力によって、出生後、半年に至ってようやく正常男児の大きさになり、両親はほっとしたのだが、おそるべき病魔はいつまでも私の両親を喜ばせてはくれなかった。
いったい、どこでどのようにして感染したのかわからないが、いつの間にか恐ろしい、糸状菌が私の頭に棲みつき、頭一面に物すごい炎症性腫瘍物を、ところせましと発生させたのである。
p5
後で両親から聞いた話によると、全く目をおおいたくなるような、見るも哀れな状態であったということだった。
私はその苦しさのためか、昼夜を分かたず泣きっぱなしで、どうにもしょうがなく、手がつけられなかったということだった。それにいくぶん熱もあったので、母は私を背負って、当時、東町というところで開業していた健生堂外科医院へ診察をうけに行った。
私の頭の様子を診た院長は、たいした説明もせず、いきなり頭をヨードチンキで消毒すると、メスを取り上げ、その炎症性腫瘍物を片っぱしから切り破り、押しつぶしていった。
恐ろしい荒療治に母は大いに驚き、何度も叫びに近い声をあげたという。荒療治が終ったあとも、院長は私の頭に何か分らぬ軟膏をつけ、包帯をしただけで注意らしいことばひとつなかったとか。母は泣き叫ぶ私を背負って、母自身、泣きたいような不安な心で医院を出たということであった。頭を白い包帯でぐるぐる巻きにされた私は、傷のいたみと、うっとうしさのためか、その後もずっと泣きつづけていたそうだ。
p6
母は、私が荒療治を受けたことが刺激になって、高熱を発しなければよいが、と懸念していたのだったが、やはり母の不安な予感が的中し、その夜から丸五日間、私は昼夜を問わず40度以上の高熱状態がつづき、幾度も生死の境をさまよっていた。
母は軍医総監築田多吉博士の書いた、いわゆる赤本、と呼ばれている『実際的看護の秘訣』という家庭用の、通俗医学書と首っぴきで、私の看護に寝食を忘れて没頭したようだった。とはいっても、朝夕は家業の旅館の調理場に立って包丁を握り、調理、家事一切をとりしきっていたので、始終、私の側に付きっきりというわけではなかった。
しかし天運に恵まれたのか、そんな40度以上の高熱にみまわれたにもかかわらず、私の体は一週間ほどたつと、ようやく快復のきざしが現われ、熱も次第に下降し、流動食を口にするようになっていった。
ところが、なんということであろう。私の体は三日間の猛烈な発熱から解放されたかと思ったら、両眼に白いかすみがかかってしまったのである。
p7
母の話によれば、澄み切ったつぶらな瞳が、ほんの僅かな日時の間に白濁してしまったのだそうだ。母の驚きようはひと通りのことではなかったと思う。
終日、飲酒に耽溺していた父は、私の両眼が失明の恐れがあるような病変を引き起したことに関しても、それほどの驚きを見せなかった。驚きを見せないというよりは、むしろ無頓着であったといった方がいいような、そんな程度の関心しか持ち合わせていなかった。母はそんな父の無関心さ、無神経さを心の奥でうらみ悲しみながらも、一応の相談はしていたようだった。
しかし、しまいには相談することもやめて、母自身の意志で、当時、秩父郡は野上町で開業していた、落合眼科医院へ私を背負って診察をうけに行った。医院での受診で、母は不安を心の奥にひそめながらも、明るい未来が予測される言葉を、院長からいって欲しかったのである。
院長のことばは、
「お気の毒だが、この子どもの眼は両方とも今は助からない。だが、15、6歳になったら、あるいは手術によって開眼させてあげられるかも知れないから、そのころになったら、また連れて来なさい」という、冷たい響きをもったものであった。
p8
そのときにつけられた診断名は先天性白内障ということだったが、その当時の白内障の処置は、すべからく、完全失明の状態になってから、手術をするという方式をとっていたのである。
しかし、母にはどうしても落合医院の院長の言葉を素直に信じ、私が15、6になるまで待っている気にはなれなかった。そこで知人を頼んで東大眼科の診察を受けに行ったのだった。
ところが、東大の診察では、
「余り期待はできないが、いま一年ほどたって、子どもの体の健康が回復したら、手術してみましょう」
という言葉が返ってきた。
それを聞いた母は大いによろこび、それから約一年、私の健康回復のために、献身的な努力を重ねてくれたのだった。たしかに東大眼科での診断当時の私の体は、頭の糸状菌による炎症性滲出物と、高熱のために、かなり体が衰弱していたのであるから、そのようなことをいわれても仕方がなかったのである。
p9
私の両眼は、東大眼科医の診断どおり、それから一年後の手術によってどうやら開眼し、視力的にはかなりの不足はあったが、日常生活がどうにかできるところまでに回復したのであった。
落合眼科医院で、院長から通告された私の眼病のことについての話を聞いた父は、私が男児として生まれたというのに、未熟児であり、その上にまた視力障害児であったということを知って、大いに落胆し、一時は常軌を逸したのではないかと思われるほど荒れ狂い、連日連夜、飲酒に耽溺し、母に乱暴をはたらいていたようであった。
30歳になったばかりの、若い陸軍中尉の位をもって退役していた父には、未熟児と失明という二つの因子が、息子の将来をおぼつかなくさせる、ということで不安でたまらなかった。その父のいいようのない悔しさが、たくましい胸の中をかきむしっていたのに違いない。
p10
しかし父は、私個人にはただの一度も冷たい態度をみせたり、口汚いことばで罵倒したり、また拳でなぐりつけたりするようなことはなかった。それだけに父は飲酒におぼれ、自分の心の弱さを慰めていたのであろう。
だが私の両眼が、手術によってある程度まで視力が回復したことを知ってからは、飲酒には相変らずふけってはいたが、母に暴力を振うようなことは少なくなっていったようであった。
◇
その当時、満州で特殊的な地位を主張する日本政府と軍部は、対中華民国政策で、蒋介石の排日行動と各地で衝突し、紛争をくり返していたが、とうとう昭和6年(1931年)の9月に日本軍は、中華民国の軍隊が南満州鉄道の破壊を企て、日本軍に対する総攻撃の第一歩として、日本鉄道守備隊を攻撃してきたという理由で、ただちに行動を開始し、満州事変を引きおこしたのである。
ところが、真実は日本軍が鉄道を破壊しておきながら、それを中華民国の仕業のようにし、中華民国を悪玉化したのであった。だが、真相を知らされていない日本国民は、日本政府と軍部の虚偽の報道をすべて真実のものと受けとり、中華民国を敵視していたのである。
p11
しかし世界各国はこの日本の所業に抗議し、満州から日本軍の撤退を要請した。
だが日本軍はもちろん、理由にならない理由をもって反対し、国際連盟の会議での、42票対1票で、日本の意見は取り入れられなかった。にもかかわらず、なおも満州から撤退しようとはしなかった。
そうした情勢の中で、日本は昭和8年(1933年)3月とうとう国際連盟を脱退し、世界の孤児になったのである。国際連盟に加入している各国はみな、日本の今後の行動に注目し監視の目を光らせるようになっていった。
それでも日本は、そうしたことには一切かまわず、昭和9年(1934年)ワシントン海軍条約の期限満了のときを機会に、これを破棄することを通告し、また、ロンドンで開かれた海軍軍縮会議には、軍備の各国平等を主張し、これが入れられなかったことで、
11年(1936年)1月その会議も脱退してしまった。
そして、昭和11年(1936年)にドイツと、その翌年12年(1937年)にイタリアと防共協定を結んだのである。
p12
外交問題ではこのような取り返しのつかないところまできて、また国内では特に軍部がその勢力を拡大し、外交内政共に、次第に正統なる議会政治に弾圧を加えはじめたのである。
昭和7年(1932年)に起った、五・一五事件や、昭和11年(1936年)に起った二・二六事件は、その著明な例としてあげられる事件であろう。
◇
日本の内外で、刻々と情勢が変化している中で、両親はその毎日を忙しさに追われながらも、努力を重ねて、私が1歳6ヵ月の時期に東大病院の眼科に、またそれから2年後に、東京市立三楽病院の眼科に入院させ、白内障の手術をうけさせた。おかげで私の視力はある程度回復したが、その同じ年に、やさしかった祖母と、生まれてまだ半年にもならない妹とを同時に失ってしまった。
私にある程度の視力がでてきたので、両親は私を幼稚園に入園させようとした。
ところが視力の弱い私の入園にたいし、幼稚園側はいろいろと理由を申したてて、入園を見合わすようにいってきた。
p13
私も、私の両親もそうは感じなかったのだが、昭和11年(1936年)のころから、そろそろ幼稚園教育の中にも、軍国主義的な匂いがただよってきて、ひ弱な手間のかかる幼児や障害児は、なんとなく拒否するようなもようが見えてきつつあったのである。
そんなことを余り気にもしない私の父は、知人にたのんで無理に私を幼稚園に入園させてしまい、何も知らない私と母をよろこばせたのであった。私は最初、入園当時なんの屈託もなく、他の園児とたのしくはしゃぎながら、せいいっぱい遊びまわっていた。
だがしばらくたつと、私は教室での学習でも、園庭での遊戯のときでも、他の園児たちといっしょに行動できない遅れのようなものが、自然と現われてきたのである。母は、それが視力の弱さからくる結果である、ということを知っていたようだったが、私はまだ幼なかったせいか、全くそれには気づかなかった。
でもときおり、先生からは他の園児たちといっしょに遊戯をさせてもらえなかったり、また園児たちと他愛もないけんかをしたあとは、みんなから仲間はずれにされたりした。
p14
私は子どもながらに、変だなあ、と思うようになった。
幼児の心は正直なものであるというが、私もいったんそんな風に思ってからは、妙に周囲の園児たちや、先生たちの様子が気になりはじめた。そして気になったり、意地悪をされたりすると、すぐにその意地悪をしたり、私を馬鹿にした園児に向かって、もう然ととびかかっていった。そして私も傷ついたが、相手にもそれなりに傷をつけてやった。
「メッカチメクラ、ヨワムシヤロー」
という園児たちの悪口が、私を無茶苦茶にあばれまわらせた。
そんなことがたびたびくり返し起ったので、園長は両親を呼びだし、それを理由に退園するように通告してきた。私は退園したくはなかった、が遂に幼稚園側の強硬な意見に両親は負けて、退園させられてしまったのである。
幼稚園を追いだされた私が、それをどれだけ、いつも嘆き悲しみ、淋しいおもいをしていたことか。無意識に差別意識をもっていた園長をはじめ先生たちには、私の心などおそらく理解できなかったであろう。
p15
将来、有能な軍人になるような男児や、貞淑な妻となるような女児を、幼児のころからしっかりと教育していこうとしていた幼稚園の教育方針には、私のような虚弱な視力障害児は馴染まないところだったのである。
私はときどき、園庭の隅で一人ぼっちにさせられ、他の園児たちのたのしげにおこなっている遊戯を、じっとうらめしそうに眺め、そのたびごとに、悲しくくやしい思いをした。それでも私は幼稚園にいきたかった。だが幼稚園はそんな私の強い希望を、ふたたび聞き入れようとしてはくれなかった。幼稚園を追いだされた私は、やむなく近所の年下の幼児たちと遊んでくらすほかはなかった。
幼稚園をやめさせられてから2ヵ月ほど経ったのち、私は、はしかの洗礼をうけた。はしかはそれほど重症なものではなかったが、生来の虚弱な体の私は、10ヵ月近くもふらふらと日を送るようになった。そのために、小学校の入学を1年遅らせることになってしまったのである。
p16
私の入学が一年遅延した理由として、学校側は、
「視力に障害あると、学習の面でも、その他の行動面でも、いろいろ不都合が生じてくるし、また友人をつくるにも支障がある。それに人一倍、体が虚弱では、その面からも問題があり、おそらく毎日通学をつづけることはむずかしいから、もう一年入学をおくらせる方が得策だろう」
という意見を、父を呼び出していったのである。
父は最初のうちは、その学校側の意見に強固に反対し、ぜひ私を学校に入れてもらうように懇願した。しかし学校側の意はきわめて強硬であったので、ついに父もやむなく学校側の意見に従わざるを得なくなり、来年を約して引きさがってきたのであった。
どちらかといえば父は、私に対して盲愛的なところがあったので、学校側からそのようにいわれると、私がかわいそうになり、最もな意見だと思いこんでしまった。それを聞かされた私は、なんとなく以前の幼稚園のときの例に似ているような気がして、釈然としないものを感じていた。
◇
p17
その当時中国では、満州事変後、統一傾向を強め、抗日運動に全民衆、全党派が協力し、蒋介石の指導のもとに国家意識を盛り上げていた。両国の衝突は、昭和12年(1937年)の7月7日に、北京郊外の盧抗橋で起った一発の銃声によって開始され、それが支那事変となって拡大されていったのである。
開戦当時から勢いにのった日本軍は、調子よく各地で勝利をおさめ、わずか半年ほどの間に北支五省のほとんどを占領したのである。両国政府は一応事件の不拡大と極地解決の方法をとり、折衝したが、日本側の政府と、独立した意図にもとづく軍隊の独断行動によって、その両国側の努力は成立せず、戦乱は北支から中支へ、更に南支まで拡大していったのである。
日本国中はこの大勝利に、昼は旗行列、夜は提灯行列をもってうち興じ、いつ終結するかもしれない戦争の泥沼に追いやられるとは、いささかも気がつかないで、ただただ戦果、戦果に酔いしれていたのであった。
一方、ヨーロッパに於ては、ドイツ及びイタリアがベルサイユ体制の破棄をし、ヨーロッパ新秩序の自立を理由として、各地に侵略を開始していたのである。
p18
昭和11年(1935年)イタリアは、対エチオピア戦争を起し、ドイツは再軍備を宣言し、翌11年(1936年)にはラインランドに進駐し、13年(1938年)には、オーストリアを併合し、14年(1939年)にチェコスロバキヤを占領した。そしてヨーロッパ全地域にわたり、侵略の手をのばしていったのである。日独伊三国の防共協定は、12年(1937年)に成立され、昭和15年(1940年)の9月にはついに、日独伊三国軍事同盟が結ばれ、ますます世界の情勢を悪化させていった。
◇
入学がまる一年遅延となった私は、虚弱なことと視力障害があったために、同じ年の、すなわち1年生に入学したものとは、友だち関係をもつことができなかった。そこで仕方なく、私は1つ年下の幼稚園にいっていた、宮前京子という女児といつも遊んでいた。
京子は私の家と三軒ばかり離れたところに店を出している、秩父の町では一流書店の娘であった。なかなかの器量よしで、可愛いい少女だったが、とても元気だったので、虚弱な私は時おり京子と口げんかなどをすると、しまいにはその場へ押し倒されたりした。
p19
そんなとき京子は私の胸の上に馬乗りになり、体を押えつけながら、
「こんな弱虫では、とても強い兵隊さんにはなれないわね」
といって私を見下ろし、勝ちほこったように笑っていた。
男児としては誠にはずかしい話だったが、当時の私には馬乗りになっている京子を跳ねとばすほどの体力はなかったので、やむなく無条件降伏をする以外はなかった。京子とは時おりそんな他愛もない争いをしていたが、ふだんはとても仲よしの友だちだった。
ところが私が一年遅れて小学校の1年生に入学して間もないころ、京子は急性食中毒で幼い生涯を閉じた。京子を失った私はしばらくの間、京子のことが忘れられず、京子の家に遊びに行ったりして気をまぎらわしていた。
だがその年の夏休みに入るころには、ようやく元気をとり戻し、体力がついてきたことも手伝って、同年齢の男児たちとも一人前に遊べるようになり、戦争ごっこや、チャンバラごっこ、とんぼ採りや水遊び、山登りなどにも徐々に参加していった。
p20
昭和の大横綱といわれた双葉山が、ちょうど全勝街道を幕進しているころであった。それは当時の戦争気分にマッチして、双葉山の連戦連勝は、日本軍の連戦連勝の姿を相撲の世界に象徴したものであると本気に考え、いいまわっている者さえあった。
彼らは、日の本の国、日本は、決して戦争には負けない、あるのは勝利のみである、とか、神々が見守っているから必ず戦争には勝つ、といい、双葉山が負けないのは勝利の神がのり移っているからだ、などといって、戦勝妄想に酔いしれていたのである。
昭和14年(1939年)の春場所四日目に対戦した安藝ノ海の外がけによって、連勝は破れ、記録は69連勝でとどまったのだが、妄想めいた勝利への神がかり的な意見や主張は、いっこうにやまず、指導者の口から当然のことのようにいい放たれていたのである。
p21
◇
私が一年遅れの7歳で1年生になったときの小学国語読本は、昭和8年(1933年)に文部省が改定したものであったが、その最初のページには、サイタ サイタ サクラがサイタ と太い文字で黒々とはっきり書かれてあり、その下に桜並木のような絵が描かれてあった。
私はそのとき、陸軍小尉の位をもって退役していた担任の、新井耕平という教師から、「さくらの花は日本を代表する花でありますが、また、この花は日本男児の心を映している花でもあるのです。なぜかといえば、さくらの花はぱっと咲いて、ぱっと散るからです」という話をきかされたことを、不思議にもはっきりと記憶している。
担任が軍人だったから、私は小学校の1年のときから忠孝とか、愛国精神とか、男児は偉い兵隊になってお国のために死ぬのがよいのだ、とかいう言葉を始終やさしい話のなかできかされていた。今になって考えてみると、当時の文部省が、小学校のまだあどけない児童のころから、軍国教育をしていこうということを、いかに綿密なる計画のもとになされていたかが分るのである。
p22
しかし当時、教壇に立つ教師の中の何人が、このことについて気づいていたか、もし気づいていた教師がいたとしても、それは微々たるものでしかなかった。またたとえそれに気づいた聡明な教師がいたとしても、それについて異議を唱える教師が何人いたか、それは全く皆無に等しかったのではないかと思う。
なぜなら、そんなことを主張の材料にすれば、反戦思想家として特高警察につけねらわれるからである。だから大部分の教師は、あどけない児童を前にして「さくらの花はね」と真面目な顔をして、まことしやかにさくらの花の意義について、話をしていたのであろう。
小学校の低学年でさえ、すでにこんなぐあいであったから、小学校の高学年や、旧制中学校や、旧制女学校では、教育勅語が修身の教科書の中にのせられ、真面目な国粋主義者、軍国主義者として指導されていたのである。世界の平和のために、とかいう妄想的な途方もない目標を信念に結びつけて考えさせられ、最後には“一旦緩急アレハ義勇公に奉シ”というところまで指導されていた。
p23
正直をいえば、当時の一般庶民の多くは、日本がアジアの民族の繁栄をもたらす、もっとも秀いでた国であると思いこんでいたのである。
その当時、秩父の町では小学校は全学年男女共学であったようだ。私が小学校1年から3年までは、男女共学で、学校の種別も、尋常小学校という名称で呼ばれるものに属していた。
ところが昭和16年(1941年)の4月からは、尋常小学校が国民学校という名称にかわり、小学生はみな大日本帝国の少国民として位置づけられるようになったので、男女共学も小学校3年までで、4年以上は男女共学は廃止されてしまったのである。
そして帝国主義のもとで、少国民としての責務を教育勅語を題材にして、より徹底して教育されていったのであった。
国粋主義にもとづく軍国教育が濃厚になってきたので、体格のよい腕白小僧は、多少学業の成績が悪くとも、若い活気にあふれる教師たちからは、特別な目をもってみられていた。
p24
だから私のような虚弱児は、いつもそれらの腕白小僧に軽蔑、冷笑されていたのである。しかし年齢の長じた人間味豊かな教師たちの何人かは、そうした傾向に全面的には従わず、軍国教育という枠の中でも、むやみに腕白小僧のいき過ぎた態度をほめそやすようなことはせず、それなりの厳しい指導で彼らに罰を加え、また手もとに彼らを呼び寄せて諭したりなどしていた。
だから私のような虚弱児でもまだ小学校の低学年のころは、目に見えてはっきりと差別されたり、非国民のあつかいをうけたりするようなことは少なかった。
それに上級学校へ進もうという者のなかには、成績がよいばかりではなく、人間的にもすぐれた者がいたので、虚弱児や障害児は、ときには彼らの善意に救われてたのしい学校生活を送ることもできたのである。
そうした中で私は、小学校の3年のとき、順天堂病院の眼科でうけた白内障の再度の手術に成功した。それは両眼の視力がならんで0.2というところまで回復するという、劇的なよろこびであった。そしてすこしずつ学業にも目を向けるようになっていったのである。
p25
◇
ちょうどそのころ、米英両国は、日本の政策遂行のための武力行使を否認し、国際条約の遵守、通商上の機会均等、世界平和の意義を主張した。
しかし日本軍は昭和14年(1939年)に海南島を占領し、更に南進して翌15年(1940年)北部仏印に進駐し、16年(1941年)には、南部仏印に侵略の手をのばしていったのである。
米英両国はこれに対し、中華民国に、武器や物資の援助を盛んに行なうようになり、中華民国の抗日運動を支援していたのであった。
一方、14年にはノモンハン事件等で、ソビエトとの国境紛争に苦戦を余儀なくされていたが、16年(1941年)4月、日ソ中立条約を結び、一応、北満方面の治安をもたらすことになった。
しかしその年の8月に日米会談が開始されたが、会談は良好な方向には進まなかった。すなわち、それは日本の軍備拡張と、戦争計画が外交交渉とは全く別個に進められていて、それが米英を含む、連合国に大きな疑心と抗日感情を植えつけさせる結果となったからである。
p26
昭和16年(1941年)の10月に、東条内閣が成立することによって、日本軍の暴挙ともいうべき侵略活動が、いっそうあらわになっていったのである。
そして遂に、昭和16年(1941年)の12月8日未明、大東亜戦争に突入する、という結果を日本は自ら招くことになった。米英に宣戦を布告する直前に、海軍の艦載機はハワイ真珠湾を攻撃し、また10日にはマレー沖で壮烈な大海戦をくりひろげ、それぞれ米英の連合艦隊の中枢部に大損害を与えた。
一方、中華民国や仏印においても、大規模な作戦行動が開始され、アジアの巷に戦いの火花がとび散っていった。ラジオからは開戦と同時に、たてつづけに調子のいい軍艦マーチが鳴り響き、戦果が次々と報道された。
きんきんした金属性の東条首相の声が、ラジオからやたらに聞えてきて、国民にがなり立て戦闘意欲を湧きたたせた。開戦して間もないころの日本軍の勢いは、誠にすさまじく、その年の暮には香港を、年が明けて昭和17年(1942年)の1月にはマニラを、そして2月には英国のアジアに於ける鉄壁の要塞といわれていたシンガポールを陥落させた。
p27
この大戦果は日本国民をいやが上にも歓喜させ、またまた昼は旗行列、夜は提灯行列という派手な騒ぎが展開された。そして国民は全く勝利の歓びにひたり切っていたのである。
私も当時日本軍のはなばなしい勝利の姿を撮影したニュース映画や、そのダイジェスト版をよろこびいさんで観に行ったものである。日独伊三国同盟が成立した昭和15年
(1940年)は、紀元二千六百年にあたっていたので、国中がその慶事に湧きかえっていた。 “金鶏輝く日本の”という一節から始まる“紀元二千六百年”の奉祝国民歌が、国中の老若男女のあいだで歌われ、いやがうえにも日本の国家意識が盛り上っていった。
そうした一方、庶民の生活の上には、あらゆるものに少しずつ統制がしかれ、配給制度が確立し、隣り組の団結が強要された。 “贅沢は敵だ。”とか“欲しがりません勝つまでは”“パーマネントはやめましょう”などといった流行語が次第に叫ばれるようになっていった。
p28
◇
私は思った以上の視力の回復をみたので当時、少年少女の間で愛読されていた小説を読んだり、夢中で絵筆をふるって水彩画を描いたりした。
ちなみにその当時、私が読んだものをあげてみると、山中峯太郎の「アジアの曙」「大東の鉄人」「太陽の凱歌」「空襲機密島」「黒星博士」「見えない飛行機」「敵中横断三百里」。南洋一郎の「決死の猛獣狩」「吼える密林」「緑の無人島」「謎の空中戦艦」「潜水艦銀竜号」「魔海の宝」。
また海野十三の「浮かぶ飛行島」「太平洋魔城」「宇宙戦隊」「大空魔艦」「海底大要塞」。平田晋作の「新戦艦高千穂」「昭和遊撃隊」「我等若し戦はば」などという冒険ものが多かったが、なおそのほかに、吉川英治や、高垣眸、大佛次郎、千葉省三、村上元三などが書いた時代小説も読んだし、また吉屋信子、水島あやめ、北川ちよ、横山美智子らが書いた少女小説も読んだ。
そのほかに佐藤紅緑、久米正雄、富田常雄、サトウハチロウ、佐々木邦らの書いた少年小説も好んで読んだ。江戸川乱歩の二十面相シリーズは、特に面白く夢中になって読んだものであった。
p29
これらの小説のなかで特に軍事探偵、冒険小説は学校の担任教師が、進んで読むことを奨励していた。私はその奨励されたものはことごとく読んだが、それは進められたからというより、私自身が虚弱児であり障害児であったので、絶対に兵隊にはなれない、という男子としての悲運を、小説を読むことによって、夢を実現させようと思ったからである。
私はそうした小説のなかで、平田晋作の書いた「われ等若し戦はば」は特に興味を持った。それは単なる国粋主義の意図の強い、軍事物語的な日本軍礼讃の物語ではなく、冷静で且、客観的な科学性のある物語であった。
そして精神主義にとらわれ科学性の乏しい日本の軍備の未来に疑問を投げかげ、将来が危ぶまれる部分が匂わされてあったり、現在の軍事科学の研究ていどでは、やがては欧米の科学技術にわが日本は劣るのではないか、と書いてあったからである。
だがこの小説はそれがゆえに発売禁止となったようで、平田晋作は自由に文筆活動ができなくなった、ともいわれている。
p30
とにかく当時は、テレビジョンもなかったので、読むこと以外に、たのしみながら知識や情報を導入する方法はなかったのである。
私がそれほど夢中で小説を読みあさった理由の一つは、それらの本の中にのせられている挿絵に興味があったからで、それは写真のような白黒二色で描かれたものであったが、とても素晴らしく読む意欲をそそるのに充分であった。
その当時、健筆をふるっていた樺島勝一、鈴木御水、村上松次郎、伊藤幾久蔵、梁川剛一、などがこぞって描いていたのだから、無理もないことである。私の瞼の裏に、今もなおその印象が強く再現されてくるのである。
挿絵といえば、田河水泡の「のらくろ」や、「凸凹黒兵衛」、島田啓三の「冒険ダン吉」、横山隆一の「フクちゃん」といった漫画もなかなか面白かった。漫画ではほかに、著者名は忘れたが、「チビワン突貫兵」「小ぐまのころすけ」なども忘れられない名画だった。
これらの漫画は、小学校の低学年のとき、講談社の絵本や、各種の童話といっしょに読んだものだ。
p31
「幼年倶楽部」という雑誌もまたなつかしい読み物であったが、これもまた私を夢中にさせた。
戦時体制がきびしくなった昭和17年から18年(1942年から43年)になると、私も人並に「少年倶楽部」だけではなく、「航空少年」や「飛行少年」などという、航空機、空軍関係の雑誌を求めるようになり、またときとしては、成人用の雑誌である「講談倶楽部」とか「キング」「日の出」といった雑誌などもかじり読みするようになっていった。
私は絵を描くことが好きだったので、そうした小説の挿絵を写したり、想像画を描いたりして一人たのしんでいた。そのなかでも、特に相撲の四十八手や、力士のブロマイドなどを描いたりするのが好きであった。水彩画に夢中になったのは、昭和17年(1942年)以降のことである。
戦勝を祈るための神社参拝が励行されるようになったのは、いつごろからか記憶していないが、毎月1日と15日にきちんと、児童生徒一同が足並をそろえて、秩父神社に参拝した。
p32
太平洋戦争がはじまると、出征兵士たちは、秩父神社に参拝し、軍歌に送られて出陣していった。そのため私のような少年たちも、いつの間にかおどろくほどの軍歌をおぼえた。
日本陸軍の歌、戦友、日の丸行進曲、愛国行進曲、国民進軍歌、愛馬進軍歌、燃ゆる大空、索敵行、大空に祈る、若鷲の歌、決戦の大空へ、荒鷲の歌、加藤部隊歌、勝利の日まで、特幹の歌、空の新兵、露営の歌、麦と兵隊、ラバウル海軍航空隊の歌などなど。
こんなたぐいの歌が数多く作詞作曲されていた。
昭和19年(1944年)の終りのころだったとおもう。勝ち抜くぼくら少国民、という歌が作られたとき、学校の校長はたいへんこの歌が気に入り、式典にはいつも児童生徒に歌わせていた。
今から考えれば、どうということはないのだが、負け戦にかたむいていた、その当時の国民、とくに少国民である私たちの意識を鼓舞させるには、適当な歌だと思ったのであろう。
p33
勝ち抜くぼくら少国民
天皇陛下の御為に
死ねと教えた父母の
赤い血潮をうけついで
心に決死の白だすき
掛けて勇んで突撃だ
こうした歌詞を読んでみると、確かに哀調をおびた短調の曲と相まって、旧制師範学校出の校長の好きになりそうな歌である。それにしてもこの歌を、飽きるほど歌わされたので、最後にはいやになったものだ。
映画と歌では時どき関連し合ってよくヒットすることがある。たとえば暁に祈ると愛馬花嫁という歌ができてから、同じ題の「暁に祈る」という映画ができたり、若鷲の歌や決戦の大空へという歌をいっしょにして「決戦の大空へ」という映画ができたりした。また索敵行と大空に祈るの二つの歌が主題となって「愛機南へ飛ぶ」という映画ができる、というぐあいに、数多くの映画が、東宝や松竹、または軍部が指定した映画会社でつくられた。
p34
私は小説も読んだが、映画もよく観に行った。今でも記憶している映画の題名をあげると「燃ゆる大空」「空の新兵」「西住戦車長伝」「加藤隼戦闘隊」「麦と兵隊」「土と兵隊」「雛鷲の母」「国際密輸団」「奴隷船」「海軍」「海賊旗吹っとぶ」「マレーの虎」「シンガポール総攻撃」「マレー戦記」「ビルマの戦記」などがあり、またほとんどドイツ映画であったが、外国映画にもなかなか素晴らしいものがあり、「世界に告ぐ」「潜水艦西へ」「ビッツオ爆撃隊」「急降下爆撃隊」などがそれであった。
小学校に在学しているときには、戦争中でもあったためか、遠足なども心身の鍛練を加味していたので、なかなかきびしいところがあった。すなわち遠足といえば、遠い足と書く文字のごとく、何里かの道を一回も乗りものに乗らずに歩きとおしていたし、それにその距離は学年が上るごとに、一里増すことになっていた。1年は一里、2年は二里、というぐあいに増していき、6年は六里、そして最高学年の高等科2年は、八里ということになっていた。
p35
それにこの最後の八里は、夜行軍をすることになっていた。しかしそういうものだと思っていたから、それほど不平もいわずに歩いたものであった。秩父盆地は平坦な道が土地柄上少ないので、同じ一里の距離でもかなりきつい道のりで、大いに脚力を鍛えられたものである。春と秋の遠足はきついところはあったが、一面では美しい景色の自然に親しむことができるので、たのしくよい経験でもあったと思っている。
◇
昭和17年(1942年)の4月を迎えるまでに、日本軍は南洋方面の主たる島々をことごとく占領し、石油資源の確保にこれ努めた。連合軍はこれに対し徐々に反撃の力を蓄積し、4月18日には大航空母艦ホーネットから、ノースアメリカンB25を飛び立たせ、東京を初空襲し、真珠湾攻撃にまさるとも劣らぬ奇襲攻撃を加え、日本国民の心胆を寒からしめた。
その後5月には、マッカーサー元師が、南西太平洋連合軍指令長官に就任し、第一線の指揮にあたり、5月に珊瑚海、6月にはミッドウェーの海戦をもって、日本海軍の誇る連合艦隊の三分の一を壊滅させてしまった。
p36
日本海軍はこのミッドウェー海戦での作戦の失敗から、4隻の航空母艦を失い、今後に大きな傷あとを残したのであった。
しかしこの大打撃をうけた真実の報道はなされず、日本国民には軍艦マーチで景気をつけた虚偽の報道がなされていた。ラジオから流れるマーチにつづく報道をきき、日本国民はそれが虚偽のものだとは知らず、有頂天になっていたのであるから、まさに想像を絶する不幸という外はない。
かくして、すさまじくも勇ましい日本軍の勝利に歓喜しながらの進撃は、このミッドウェー海戦の前までのことで、この海戦の敗北によって、大いに狂いを生じたのである。そして次第に増大してくる連合軍の圧力に、苦しい戦闘を強いられるようになっていった。
◇
小学校、いや国民学校の5年に進んだばかりの私は、もちろん日本軍が太平洋上でそんな戦局の中にいるとは、すこしも知らなかった。
p37
だから大本営の虚偽の発表をそのまま真実のものと思いこみ、軍歌や国民歌謡を歌いながら、少国民の一人として、私なりに真剣に勝利を神に祈願し、回復した視力を生かして勉学に励んだものであった。
しかし私の視力の程度では、まだまだ充分な活躍なり勉強なりはできなかったので、ときには無理解な級友にひどい目に合わされることもあった。五年になって増えた教科や体育のほかに、新しく武道として柔道と剣道が加わってきたし、また教室での学科には地理と歴史が加わり、一日の授業時間数もまた、一週間の総時間数もぐんと増加していった。
虚弱体質がまだ幾分残っている私には、教室での地理や歴史はまだまだよかったが、屋外での柔道とか剣道は誠に苦労したもので、特に眼鏡をはずして面をかぶらなければならない剣道は、どうにも好きにはなれなかった。
それでもどうにか尻の方からついていくことだけはできたのである。武道の方は馴れるに従って、見よう見真似でどうにか人の後についていけたが、勤労奉仕として行なう農作業の手伝いは、どうにもうまくできなかった。
p38
だからそんなときは、農家出身の友人にいろいろ指導をねがうのだが、俄先生はいばりくさって、私はよく殴られたので、少しも愉快ではなかった。
「手前はめっかちだから、半人前もできやしねえ、全く困った奴だ。こいつはほんとうに非国民だ」
といっては物陰につれていかれて、よく殴られたものだ。でも私としても殴られてばかりはいなかった。作業場で同じくらいの体つきの相手には、憤然として殴り返してやり、また噛みついたりして大喧嘩になったりしたこともあった。
「戦争に勝つには国民全部が力を合わせて戦うのだ、作業も戦いのうちだから、真剣に怠けずにやれ」
と担任の教師はそういって、麦刈り稲刈り、苗代の草とり虫とり、山の開墾、桑の皮むき、麦踏みなどもやらせたりした。
私たちの小学校は、これらの作業のほかに、個人的な単位で、夏は軍馬に喰わせるための干草づくり、秋は非常食をつくるのに使用する、一人当り二升以上のどんぐり拾いが、強制的に義務づけられていた。秋のどんぐり拾いはそれほどきつい労働とは思わなかったが、夏の干草作りは骨の折れる仕事であった。
p39
決められた目標の四貫目、15キログラムの干草をつくるには、その4倍近い草の量を刈りとらなければならなかったからである。私はそれを行なうのに、工作の授業でつくった背板をさっそく利用し、それを背負って毎日のように鎌と弁当を持って、山へ草刈りに出かけた。
また初夏のころと、秋の穫り入れのころにあった農繁休暇には、農家へ手伝いに行くことを半ば強制されていた。このころは虚弱な私でもかなり丈夫になってきていたので、気に食わぬことがあれば相手に向かっていくこともあった。が、まるっきり虚弱なものはいつも差別され、軽蔑され、いじめられていた。
久保洋や山沢正行の二人は、いつもそんな作業のときはうつむいて、唇を噛みしめ、屈辱に耐えていた。でも正義の味方をする有能な仲間もいて、腕白小僧の意地悪が度を越しそうになると、いつも飛び出してきて、二人を援護してやっていた。
◇
p40
東条内閣による日本軍政治の支配下にある文部省は、政府の依頼をうけて、国民の精神づくり体力づくりに熱心になっていた。また、軍部と結託している特高警察は、刑事を各地に潜入させ、反戦思想を持っていると思われる者を見つけ次第、逮捕し、残虐極まる拷問をあたえ、半殺しの目に合わせたりして、それらの人たちの心と体を完膚なきまでに痛めつけた。
また一方では、それらの人たちの家族にいやがらせをし、国権を乱用しながら暴挙の限りをつくし、家族のものはそのいやがらせに、肉体的にも精神的にも、あるいは社会的にも非常な苦しみを味わわされていたようだった。
軍部はまた昭和18年(1943年)に入ると、文部省を通じて全国の各国民学校に、その低学年の児童を対称にして、
「あなたのお父さんやお母さんは、夜になるとどんなお仕事をしていますか」という作文を書かせるように命令し、その児童の書いたあどけない純粋な作文の中から、スパイ行為を行なっている者を探り出そうとしたようであった。
昭和18年(1943年)の4月18日、連合艦隊指令長官、山本五十六大将を乗せた軍用機は、秘密裏に飛び立ったが、暗号を解読され、米空軍の戦闘機によって撃墜されてしまった。
p41
これはノースアメリカンB25によって東京が初空襲されてから、ちょうど一年の後であった。しかし軍部は、この山本長官の死を、5月21日になるまで公表しなかった。また一方、米英連合軍はこの暗号を解読したことを、太平洋戦争が終結するまで秘密にしていたから、日本軍の暗号はいつも解読されていたということであった。
山本長官が戦死した前の年の17年(1942年)の8月、猛反撃を開始した連合軍は、ガダルカナル島への上陸に成功し、更に攻撃の手を強め、18年(1943年)にアッツ島を占領し、9月にはニューギニアに上陸、11月には、ギルバート諸島に上陸していた。
昭和19年(1944年)に入ると、マーシャル諸島までも上陸が開始され、日本軍の南方拠点といわれていた軍港ラバウルは、完全に孤立した状態になってしまった。更に連合軍は、日本軍の太平洋上の戦略拠点であったサイパン島を攻撃し、7月にはその全島を遂に占領したのである。
p42
◇
話が幾分前に戻るが、私が国民学校の5年になった17年(1942年)の初夏に、男子だけの3クラスが、秩父郡は横瀬村にある七番札所の寺に、いかなることに遭遇しても決して驚かぬ泰然自若の心、胆力が備わるようにという願いで、心身の鍛練法の一つとして坐禅を指導してもらいに行ったことがあった。
私はなんとなく坐禅というものに、何か窮屈な固苦しいものを意識していたので、内心気が進まなかった。しかしいざその場になってやってみると、それほどの苦痛ではないものであることに気がついた。午前午後の2時間ずつの行が、それほどいやでも苦痛でもなく、無我の境地に入れそうな気がした。
だからその翌日にはなんの低抗もなく、朝40分の坐禅の行に親しむことができた。その後毎朝、40分ほど坐禅を組むことを嫌わずに行うことができた。この小学校の坐禅の行への団体参加は、当時の三大新聞に写真入りで載せられたものであった。
p43
心身鍛練といえば、昭和18年(1943年)の1月の大寒に心身鍛練期間、と銘うって授業前、早朝マラソンを行なった。それは凍てつく冷たい空気の中を走るので、容易なことではなかった。だから虚弱なものは男女に限らず、途中から落伍するものがいて、教師が自転車にのせて学校へ運んで行った。
私も虚弱な体質の方だったので、いつ参るかと毎日気になりながら走っていた。
“勝利の日のために強靱な心身を”という、努力目標はいいが、このマラソンはかなりきついものであった。
そんなある日、その日も空気がとても冷たくひえ切った朝であった。私は他の友人といっしょに、ワッショイ、ワッショイという掛け声をかけ合い、白い息を吐きながらとっとと走っていた。そのうちふと、前を走っていた山沢正行が、どんどん遅れて最後の方になってしまったのを見た。
私は自分が走るのが精いっぱいだったので、どうしてやることもできなかった。気にしながら走っていると、突然、
「山沢が倒れた」という声が背後からきこえてきた。
p44
振り返ると、山沢は冷たい道路にうつ伏せに倒れてあえいでいた。私は何もできないけれどもすぐにかけ寄った。が、もうそのときは最後部にいた三人の友人の手によって助け起されていた。
三人の友人は、それから交代しながら山沢を背負って走りつづけ、見事に予定のコースを完走した。校長以下、何人かの教師がこれを見て感動し、マラソンのあとの集合のときに、山沢正行の努力と、三人のけなげな友情をほめたたえた。
このことは翌日の朝刊に写真入りで、“心身鍛練期間の花”というタイトルで大きく報道されていた。
太平洋戦争が開始されてから、庶民の娯楽に関するものが際立って制限され、カフェーやダンスホールの数が、めっきり少なくなった。そこで一般庶民は、盆踊りにうち興ずる以外、他に楽しみはなかった。
そういうこともあってのことか、昭和17、8年(1942、3年)には、町や村の祭りのたびごとによく盆踊りが催され、櫓だけは景気よく高いのが立てられた。私は秩父音頭を、あちらこちらに招かれて行っては唄っていた。
p45
ところが時勢を反映してか、唄の文句も戦時的な匂いの濃厚なものが、時おりふくまれていた。
早くやりたいあの子とこの子
無事に育てて海と空
無理かしらぬが男を生めと
主の便りは戦地から
お前出て征け敵撃滅に
俺は職場で力こぶ
などというのがあった。踊り子も男はしるし半纏、女はもんぺ姿というスタイルで、それでも一所懸命踊っていた。
祭りに来るサーカスも、昭和18年(1943年)の秋にはすべて猛獣たちの姿が消え、東京の上野動物園にも、猛獣の姿が見られなくなった。これは空襲をうけたときの、安全処置のために毒殺、または餓死などさせたということだが、それにしてもかわいそうなことをしたものだと思う。
p46
しかし戦局はもうそんなところまできていたのだから、ある意味では無理もないことだが、真相を知らされていない一般国民、特に私たちのような少国民にとっては、たまらなく、つらい哀れな処置で、動物のために友人の中には涙を流して悲しがる者もいた。
◇
サイパン島の敗北は、東条内閣の総辞職となり、代って小磯内閣が誕生した。サイパンを基地としたアメリカのB29爆撃機は、大編隊を組んで日本本土の空襲を、その年19年(1944年)の秋ごろからはじめたのである。
10月には台湾沖で大海戦が行なわれ、日本軍は大打撃をうけた。次いで連合軍はフィリピンを攻撃、更に12月にはレイテ島を攻撃して、決死の大海戦がくりひろげられたが、日本海軍は、ここでもまた大きな損害をうけることになったのである。
このころから庶民の間でも、本土決戦ということもあり得る、ということがささやかれるようになった。防空演習は本土空襲が始まる4年も前の、昭和15年(1940年)のころから、町内隣組の単位ではじめられていた。
p47
最初、私が防空演習をみたのは、小学校の3年のときであった。防空演習というのは、あとから考えてみると、きわめて幼稚な方式で行なわれていた。それは爆弾や焼夷弾が落ちて火災になった家屋を、バケツリレーで水をかけて消火するというやりかたや、棒の先に縄をつけて作った大きな火はたきを、水で湿めらせて火を叩き消そうとする方式で、江戸の火消しの再現のように思われた。そこには、雨あられのように大量の爆弾や焼夷弾が落ちてくることなどは、全く想像だにされていないものであった。
たとえ若し想像されていたとしても、防空演習のねらいは、果してほんとうに防空のために行なわれていたのかどうか、極めて疑問を感ずるもので、おそらくは、隣組単位の庶民の団結と、米英に対する敵愾心を燃えあがらせるためのものではなかったろうか、と思われてならない。
若しそうではなくて、本当に防空のために考えて行なっていたのだとすれば、余りにも貧弱な構想であり、もうその時点で日本は、米英に勝ち目がないと決めつけても、間違いのない事実だったのである。
p48
しかし、現状の日本の大勢を全く知らされていなかったので、庶民はそうした幼稚な防空演習にばかばかしいような気がしながらも、どこかに真面目な意識をもって、真剣にとり組んでいたのである。
◇
昭和18年(1943年)から19年(1944年)になると、真の意味で人間味のある、有能な教師は戦場に引き出され、その中にはあえなく戦死を遂げ、征きて還らぬ人となった教師もいた。そのため学校は次第に実力のない中学校や女学校上りの、いっときは不良少年ともいわれていたような者が、代用教員として教壇に立つようになっていた。
だから自然に児童生徒の考え方も、勝つことの意識に通じることであれば、何をしてもいいという恐ろしく乱暴で危険な優越意識や、攻撃意識が強くなっていった。これがもっとも、戦時国の少国民の考え方として、大切なことのように植えつげられていったのである。
p49
またちょうどそのころ、児童生徒の中でも有能な者は旧制中学校へ進み、高等科1年になった者の中には、そんな代用教員と肩をならべるような、粗野で、無分別な、体格だけがよく、考え方のできていない生徒がかなりいたので、学校の中ではいろいろな問題が起こっていたのである。
こうしたいろいろな問題、すなわち盗難、暴力、リンチなど、戦時下であったので、現在の日本の中学校あたりに起こっているような激しいものにはならなかったが、当時としてはかなりのことが行なわれていたようだ。
私のような虚弱体質がまだ残り、障害児であるようなものは、いつもにがい不快な経験をしなければならなかった。力の強い上級生が、弱い下級生を呼びつけては、
「手前はそんなことでは、天皇に忠義をつくせる日本人にはなれねえぞ」
と勝手な理屈を口走って殴って泣かしているのを見ても、自分の力ではどうすることもできない。またすこしも加勢してやることのできない無力さに、歯を食いしばってそ知らぬ顔をし、卑怯者になり下って、その側を通りぬけることが何回もあり、あとで自分の不甲斐なさに悔し涙することがあった。
p50
私はまだそれほど実力が向上していなかったので、旧制中学校を受験しようとは思わなかったが、実力のある久保洋や蓼沼二郎は、当然のように中学校に入学できるものだと思っていた。
ところが、強靱な肉体を、有能な頭脳より優先する傾向にあった、昭和19年(1944年)の入学試験は、肉体的に強靱でないという理由で、この久保と蓼沼の入学を許さなかったのである。
たしかに久保と蓼沼は、体力テストでも、懸垂や腕立伏せ、鉄棒などでは、他の者よりかなり劣ってはいた。しかし二人は、筆記試験では抜群の成績を上げていたのであるから、私ばかりではなく、他の級友も合格は間違いないものと思っていたのである。
しかしその二人が落ちたことで、入学試験もいよいよそうなりつつあるか、と中学校を受験しない仲間たちでも、釈然としない心でただ、ため息のみを吐いたものであった。
p51
私は久保が心臓弁膜症を、また蓼沼が小児結核症の後遺症的なものを持病としてもっているのを知っていた。しかしそれらの持病はあるといわれるだけで、通常の学習活動には何らの支障をもきたさなかったのである。
だがしかし、それが原因の一つになって、入学試験に合格できないということになったのであった。久保と蓼沼は私の家にきて、さびしそうに、且、くやしそうに涙をうかべながらいろいろと語り、最後に口をそろえて、
「これも戦争のせいだ、俺たちは戦争の犠牲者になったんだ」
といって帰っていった。
確かに、学業の余り優れぬものが合格したのには、驚ろかされて、開いた口がふさがらない、といった感じであった。だから無神経によろこんでいるそれらの合格者たちの顔を見ていると、殴ってやりたくなることもあった。
しかしよく考えてみると、彼らも別な意味での愚かな犠牲者だと気がつき、彼らには何もしなかったのだが、少年たちに対しては、ほんとうに不平等極まる仕打ちのように思えたのである。
p52
太平洋戦争が始まって一年もたたぬ間に、連合軍は電波探知機の開発に専念し、それを各地の戦場で使用させるようになっていった。巨大な財力を科学の研究にも充分に費していたからこそ、そこにそのような結果を生んだのである。
ところが当時の日本は単なる観念的な精神力に頼ったり、生命をすてることばかりに最大の讃辞をおくる肉弾戦術にのみ頼るという方式をとっていた。もっと人間の命を大切にする戦闘方式を考えて、科学面の威力を高め、肉体はそれほど優れないが、頭脳の面では抜群に優れているものをも高く評価していたら、久保や蓼沼のような少年も胸を張って、もっている頭脳を充分に発揮する機会を見出していたかもしれない。
そうなれば、久保や蓼沼も中学校へ合格していたであろうし、戦時下であっても、虚弱者や病弱者だということで、差別をされるようなことはなかったのではないかと思う。
有能な頭脳の持ち主を、少年のころから単に病弱や虚弱や障害児ということだけで差別し、ほうむり去ってしまった文部省は、傲慢な行き過ぎた態度の軍部の前には、全く無力であった。
p53
◇
昭和18年(1943年)の5月、アッツ島が連合軍の手に陥ちたころから日本各地では、防空壕が作られはじめた。太平洋戦争は、これまでの戦争のような制海権の戦争時代より、制空権の戦争へと移り変っていたから、性能のよい航空機を数多く持っていることが、どうしても優勢になることは事実であった。防空壕を作るということは、まさに受身の体制にまわったことを象徴している、といっても過言ではない。
◇
私が六年生になってむかえた昭和18年(1943年)の夏、私は横浜にあった親類の家に海水浴をするために、姉と二人で一週間ほど行ったことがあった。
その時の海水浴は、私の視力のあるうちに経験した、最初で最後の忘れられない海水浴であった。
私はそこで早朝、すばらしく美しい水平線の向こうから、真赤な太陽がのぼってくるのを、はじめて眺めて、その荘厳さに思わず感動し、しばらくはその場を立ち去りがたい思いであった。
p54
横浜の親類の家でも、二人の叔父が日曜日の一日をつかって、家族五人が入るに充分な防空壕を掘っていた。叔父のうち、兄にあたる横田平一郎は、航空機製作所の技士長をしていたが、進歩的な考えの持ち主で、いつも家族の中では反戦的な話をしていたようである。
弟にあたる横田三郎叔父は、特にペン画に秀いでており、飛行機の絵が得意であった。三郎叔父は肺結核を患っていたので、横浜の園芸学校へ通学していた。
平一郎叔父は会社から帰ると、すぐ自分の書斉兼研究室に入ってしまい、食事以外はよほどの時にしか出てこなかった。私は許されたので、平一郎叔父の書斉へ入ってみると、その部屋には左右の壁に、天井まで届くほどの大きな書棚があり、そこには背表紙が横文字や金文字で書かれた本なども含めた、おびただしい書物がぎっしりと詰めこまれていた。
南側に面した二間ほどの窓際に、両袖の大きな机があり、もう一つ部屋の中央の大部分を占めて、図面でも引くときに使用するような、大きな机がどっしりと置かれてあった。
p55
平一郎叔父は、私には特別に反戦的な話はしなかったが、色々な写真集を見せてくれた。書棚には、私がかねてからその名を聞いてはいたが、まだ一冊もみたことがなかった飛行機の本で、「世界の翼」「烈国の軍用機」「烈強の空軍」などという大判の部厚い写真集が、古いものから順に並んでいた。叔父はそれを古いものから順に見せてくれた。
私はその夜は興奮して、いつまでも眠ることができなかった。また三郎叔父からは、何枚もの飛行機の絵を貰った。
私と姉が帰る前夜、平一郎叔父は珍らしく食事が済んでも書斉へは戻らず、食事にくるとき書斉から持ってきた秘蔵のウィスキーをちびちびやりながら、いつまでも話の仲間に加っていた。そして寝る前に私を書斉によび、「世界の翼」と「烈国の軍用機」の最も新しいものを一冊ずつ、おみやげだ、といって私にくれた。私はとびあがるほどうれしかった。
p56
そして最後に、
「戦争は相方とも勝ちたいのだから、日本が必ず勝つとはいえない。だからどんなことがあっても、命だけは粗末にするなよ。命を粗末にするような国民は、決して繁栄することはない。何らかの結果でどういう形にもせよ平和のときがきたら、その平和を大事にするんだな。むやみやたらと戦争をする国の庶民はいつも、平和を勝ちとることはできないものだ」といい、更に、
「こんど逢うときは、戦争をしていない平和なときにしたいものだな」
といって、書斉のドアを開けてくれた。
それから一年も経たぬうちに、この平一郎叔父は、会社の研究室で実験中、事故でこの世を去ってしまった。思えばあれが平一郎叔父の、私に聞かせようとした、反戦と平和を願うことばだったのかも知れない。
とにかく、その平一郎叔父の部屋でのことは、いまでも私の脳裏に焼きついていて、私に不思議な感動を残してくれたのであった。
p57
太平洋戦争が開始された翌17年(1942年)の4月になると、学校の校舎の廊下や教室の壁に、太い筆で書かれた“七生報国”“攻撃精神”“撃ちてし止まむ”“一億一心”
“必勝の信念”などというビラがはられるようになり、教師たちは児童生徒に、柔道・剣道・相撲などの道場へ通うことを奨励するようになったので、私のクラスの三分の二の者は、いずれかの道場へ行くようになった。
しかし家庭的に恵まれなかったり、虚弱、病弱、あるいは障害を身に持っている者、あまりそうしたことに意欲のない残りの三分の一の者は、そんなところにも役立たずの代ものだ、といわれて、差別的な冷たい目で見られることが多かったのである。
昭和16年(1941年)の4月に発足した日本青少年団は、戦時下の青少年たちを、学校の授業以外でその生活時中に、セミ軍隊的な規律や、行動、団体精神などを養成することを目的としていた。たとえば毎週日曜の早朝清掃、畑の肥料に使用する灰集めの仕事、冬の夜の火の番小屋での待機、巡回、農繁期における作業の手伝い、森林の開墾などの作業労働を強いられ、月一回、校庭や町の公園広場などを使用して行なわれる集会に、国旗をもって参加させられた。
p58
そんなときにはいつも“肉弾三勇士”とか、戦争に死の体あたりをした名もない勇士の話を聞かされたのだった。そして戦闘意識や、攻撃精神を培かわされ、その勇ましい兵隊の死に感動したものである。
だがそんなとき、帰り道に心ない同学年のものによく悪口をいわれ、せっかくのいい気分を阻害されて、腹立たしく悲しい思いをしたことがあった。彼等はずっと以前から私の目の障害を知っていたので、私に出合うといつも、
「お前のようなめっかちめくらは、いくらよろこんだって、あんな偉い勇士にはなれねえ」といい、私に向かって投石したりした。
私は腸が煮えくり返えるほどくやしかったが、投石をさける自信はなかったので、敵に背をむけていっさんに逃げ帰った。家に帰って自分の部屋に入ると、急にくやし涙がこみあげてきて一人で思いきり泣いたものである。
太平洋戦争のなりゆきの真実はひとことも聞かされていなかったので、純心に日本軍は毎日のニュースの時の報道のように、勝ち戦だと信じていたから、国の役に立たないわが身が、いっそう悲しく哀れに思えてならなかったのである。
p59
昭和18年(1943年)の10月に結婚した兄の武男は、12月に赤紙一枚で出征し、その後北支へ派遣されていった。私はそんな兄をうらやましい思いで見送ったものである。
久保洋、蓼沼二郎も、また山沢政行も、いつも私と同じなやみをかかえて通学していた。久保や蓼沼たちは、
「俺たちだって、好きで病気になったわけではないから、あいつらにそんなにいわれるすじあいはない」
といっていたが、私もほんとうにそう思って、たまに担任の教師に実状を訴えると、その教師は悪口をいった児童生徒を呼びつけ、怒声を浴びせ殴るだけで、根本的な解決法はなにも考えてはくれなかった。
私は、それらの児童や生徒を殴ってほしい、といったわけではなく、私たちの気持ちを彼らに伝えてほしい、と教師に頼んだのである。だがその意味するところがくんでもらえなかったようであったので、私は非常にその教師が頼りにならず不信感を抱いたのである。
p60
◇
昭和19年(1944年)の3月も終りに近くなって、私にとって眼病に次ぐ、第二の難病となった右腓骨骨髄炎という、恐ろしい病魔にみまわれた。これはまさに晴天の霹靂であった。
私はその骨髄炎の痛みのものすごさに、三日三晩泣き通し、且、もだえ苦しみ、まったく我を忘れるほどであった。最初は外傷もなく、唯、右の足関節の上部が腫脹していただけだったので、接骨院に行ったところ、その柔道整復師は、
「明日慶応大学の堀田博士が見えるから、診察してもらう方がよい」
と謙虚な態度でいった。
そこで翌日その接骨院に行き堀田博士の診察をうけた。すると博士はすぐに、
「これは腓骨骨髄炎だから、外科医院で手術してもらいなさい」
と静かな口調でいった。私は父に背負われて、上野町というところにある、柏崎外科医院へ行って診察をうけた。その三日後に腫脹の切開手術をして、あしかけ四年の長きにわたる病苦とのたたかいが、この日から始まったのである。
p61
昭和22年(1947年)の秋に、ペニシリンを使用しながら、最後の大手術をするまでに、前後、20回余りの切開手術をくり返し、ひたすら腐骨が体外へ流出してくるのを待っていた。
それはガーゼ交換の痛みの連続の毎日であり、根気よく通院をつづけなければならない苦汁の日々であった。最初の二ヵ月間は通学することもならず、病床に身を横たえ、苦痛がやわらぎ、気分が比較的よいときは、いつも読書をして気をまぎらわしていた。
夏目漱石、芥川竜之助、谷崎潤一郎、菊地寛、森鴎外、二葉亭四迷、武老小路実篤、志賀直哉などの文学と接したのは、このころで、むさぼるようにそれらの著作を読み耽り、苦痛の時を忘れようとつとめたのであった。
またようやく室内をそろそろ掴まり歩きが一人でできるようになってからは、机の大きいのを買ってもらい、水彩画を描いて気分を一掃しようと努力した。
お蔭で数多くの本を読み、たくさんの絵を描くことができたが、やはり学校へ行けないつまらなさは、どうにもしょうがなかった。
p62
ひと月ののち、松葉杖で歩けるようになり、二ヵ月ほどたって、ようやく松葉杖にすがりながら、久し振りに高等科1年の最初の授業をうけるべく、登校することができた。
教室には久保洋、蓼沼二郎、それに山沢政行の三人がいて、そろって私を迎えてくれた。私は他の級友とも話をしたが、特にこの三人とはよくお互いの家に行き来しながら、話し合ったものである。
私は毎朝、柏崎外科医院でガーゼ交換をすましてから登校することにしていたので、1時間目の授業の途中で教室に入ることが多かった。それは余りいい気持ちではなかったが、担任の先生から話が伝わっているとみえて、どの教師も叱責するようなことはなかった。学校では、体育と武道の時間は欠席せざるを得なかったが、あとの学科と図工の授業は割に出席した方だった。
高等科に進学してから、職業・商業・農業の3課目とも普通なみの成績はとりたいと思ったが、農業だけは実習があるので優れなかった。だが農業は決して嫌いな課目ではなかった。
p63
だから農場までは行けないが、学校の校舎の窓ぎわに植えられた茄子やトマトの苗の手入れや、牛・馬・羊・山羊・あひる・鶏・うさぎなどの家畜の世話をして、他の生徒の実習の真似ごとで、実習のかわりにさせてもらっていたのであった。
私が松葉杖で、かなりの距離を歩けるようになったので、久保や蓼沼はよく私を写生に連れていってくれた。高台にのぼって見下ろす故郷の町は美しかった。
セメント工場で吹き散らしている石粉に、どの家の屋根も白く染っているように見えるのも、秩父の町ならではの特有な景色だった。
写生にいくと、私はいつも足の病気のことも忘れて絵筆をふるうことができるので、うれしかった。武甲山は、裏側を白く生々しく削りとられていたが、表はまだ美しい緑におおわれ、格好な写生の対象物であった。
ところが1984年の現在では、かなりの部分が削りとられて、見るも無残な姿を晒しているということである。
写生といえば、私が通院していた柏崎外科医院には、五つほど年下の可愛らしい少女がいて、松葉杖で坂をのぼってくる私に逢うと、いつも笑いかけ、私を励ましたり慰めたりしてくれた。
p64
彼女は神尾房子といい、院長の姪で、背が大きいように見えたが2年生であった。
当時は小学校の教室が少なかったので、2年生までは2部式授業をやっていた。
そんなわけで後番のときは、彼女はいつも坂の上の母屋の門の前で待っていて、笑いかけてくれるのであった。
私は一度日曜日に招かれたのを機会に、よく神尾房子とことばを交わすようになり、次第に親しく話をするようになっていった。私が美しい彼女の姿を描くようになったのは、夏休みに入ってからのことであった。私は彼女の許しをいいことにして何枚も描き、素晴らしいと自己満足をしては、彼女にプレゼントしていたのだった。
昭和19年(1944年)の4月になると、空襲の危険をさけて都会から親せき知人を頼り、疎開してくる家族が増えてきた。そのため秩父の町にも東京弁が広まってきた。こうした縁故疎開の少年や少女は、秩父の町の子どもたちよりはるかに色が白く、垢抜けて器量よしであった。学習の面でも進歩的な意見などをいい、一見、優秀な頭脳をもっている生徒のように見えた。
p65
私の住んでいた本町にも、須山薫夫、恒行の兄弟や、島田喜美子、武男の姉弟、石橋正光、三郎の兄弟、土谷高子、真司、英司の姉弟など、大勢の新しい仲間が増えて、町はいっそう少年少女の声で賑やかになっていった。
そうした都会育ちの少年少女たちは、徐々に私たち田舎の子どもたちとも仲よしになって、お互い日本の少国民として力を合わせて戦っていこう、と誓い合い、手を握り合ったのである。
◇
昭和19年(1944年)の7月にサイパン島を占領した連合軍は、わずかな期間でこの島を大飛行場の島に変貌させた。そして秋には、B29の大編隊が、ここから飛び立ち、日本本土を空襲するようになった。日本の家屋は、そのほとんどが木造建築なので、爆弾と大量の焼夷弾で、毎夜のように地獄の修羅場と化していったのである。
日本政府は、文部省に命じて都会の児童生徒を田舎へ集団疎開させるよう強制した。
p66
なぜそうした強制命令を出したかというと、それは児童生徒の生命を国が親になり代って守ってやるという理由で、実際のところは、戦闘要員をずっと後まで残しておきたい、というただそれだけのことで、学童疎開をさせたということなのである。
◇
秩父の町にも、二つの学校の集団疎開の児童が南と北にある大きな二つの寺に、何人かの男女の教員に引率されて、それぞれ移り住んできた。
児童は私たちの町の小学校の各学年、各クラスヘ何人かずつ分けて組み入れられた。彼らはまだ日の高い日中のうちは、学習や遊びにまぎれて子どもらしい明るい笑顔をみせたり、歌ったりしていたが、日が西の山に沈む頃ともなれば、力なく疲れて寺にかえり、粗末な夕食の膳の前に坐るのであった。
そして満天の星が空に輝くころは、その空の明るさ、美しさとはうらはらに、二つの寺の境内やうしろの林の中から、はるか東京の空に向かって涙を流し、泣き叫びながら両親を呼んでいるのであった。誰だって両親と離れて遠い見知らぬ田舎の町はずれの寺などで、生活などしたくはないはずだ。
p67
たとえ爆弾でこなごなになっても、焼夷弾で黒焦げになっても、両親といっしょにいたい、両親といっしょに手を取り合って死ねるなら、むしろその方がずっと幸せだ、と彼らは思っていたにちがいない。
子どもは国の宝だ、子どもがかわいいなら、恐ろしい空襲からさけさせるのが親心というものではないのか。そうであるなら国の政策どおり、子どもを集団疎開に出して協力しなさい、それが日本国民の忠義というものだ、という理屈にもならない理屈をふりまわして、子どもの両親たちをなっとくさせ、国の政策で、親子の涙もかまわずに、その手と手を引きはなしてしまったのである。
たとえ住いは冷たいあばら屋であっても、縁故疎開で親子そろって生活できる者は、この集団疎開児よりはるかに幸せな生活だといえよう。
集団疎開の児童たちの住んでいる田舎町には、いい人もいただろうが、そういう人ばかりいたわけではない。よそ者を嫌って、いつも冷たい目で眺めている者もいた。それらの者は、児童たちを乞食か何かのように考え、畑に近づいたりなどすると、怒声を浴びせて追いちらしたりした。
p68
腹を減らした栄養不足の児童たちは、時どき悪いこととは知りながら、畑の作物をかっぱらって寺へ持ってかえり、むさぼるように生のまま噛ったりして飢をしのいでいた。そのため下痢や腹痛を起して苦しんだり、原因のわからぬ湿疹になやまされ、一日中ころげまわって苦しんだりしていた。
また栄養不足は、切り傷や炎傷の回復にもなかなか手間をとらせた。私の通院している外科医院にも、女教師に背負われた病気の児童がよく待合室に待っていた。私は外科医院で知り合った集団疎開の児童たちに、次第に同情するようになり、父から分けて貰った食糧品を、何度も自転車の荷台にのせて運ばないではいられなかった。
もうそのころは、私も松葉杖のほかに自転車に乗ることを院長から許されていたのだった。汚れ切って継ぎはぎだらけの粗末な衣服を着て、寒そうに青い顔をしてくらしている彼らの姿をみては、とてもじっとしてはいられなかったのである。私は寺に食糧品を届けた帰りみち、林や森の中で、東京にいる両親を呼ぶ声を耳にした。
p69
そのたびに胸がせまり、思わず涙することもあった。
これが当時の政府のとった、戦争後継者の確保のための政策であったのだが、そうとは知らずに日本中に分散していた疎開者はこのような屈辱にも耐えていたのである。
当時の米英のことを鬼畜米英といっていたが、まさにこれは、その鬼畜米英よりはるかにひどい仕打ちではないかと思えるのである。親子の絆を平然と断ち切ることをやってのけるということは、正常な精神の持ち主、血のかよっているものの考えることではない。
昭和16年(1941年)の4月に発足した日本青少年団は、19年(1944年)になると、少年兵の訓練の様相を呈して、その団員の中から少年航空兵、少年戦車兵などの志願者が多く出た。
航空兵をミッドウェーと、ソロモン海戦で失った日本空軍は、後継者を即時、補充する必要に迫られていたのである。だからその年から、一年わずかの養成期間で、航空兵になれる養成所としての航空機乗員養成所を緊急に設立し、青少年の入所を大々的に呼びかけていた。
p70
そのころになると、一般国民の生活は苦しいものとなっていた。特に食生活についてはきびしく、一日の一人当りの米の配給量は2合3勺、約340グラムであった。だから多くの者は、米にじゃがいも、山芋などを交えて空腹を補っていた。また粥や雑炊にして食べたり、うどん粉で作った、すいとんや、うどんを打って食したりして、ともかくその日の空腹を満たしていたのである。
当時の電車やバスの中は、非常に混みあっていて、農家からもとめた食糧品を、大きな袋やリュックに詰めて、それを背負い疲労しきった青い顔の買出しの人々が乗りこんでいたのが目についた。
“欲しがりません勝つまでは”という標語の書かれたビラが、その電車やバスに貼られていたが、その当時の庶民の生活はまことに苦しく、まさしく標語どおりであった。
また“一億貯蓄”とかいって、軍備拡張の兵器増産などに関する援助を国民に呼びかけ、国家予算の補充を押しつけてきた。
p71
学校でも豆債券を買わせたりして、より多くの貯蓄をすることを盛んに奨励した。私の級友の中には、人より多額の貯金をした、といわれたいために、家の金を盗み出してきた者もあった。こうなると、貯金の奨励も少年たちにとっては、なんのための貯蓄であるか分らなくなっていた。
当時の政府や軍部は、軍事優先の予算を組みながら、なお国民の一人一人から予算の補充をさせなければならないところまで、追いつめられていたのである。
だが、このことの真相はひと言も国民には告げられていなかったのである。
昭和20年(1945年)1月、連合軍はルソン島に上陸し、2月にはマニラを奪還し、3月には硫黄島を占領した。そして4月にはとうとう沖縄本島の攻略がはじまった。
比島決戦の歌、沖縄決戦の歌という勇ましい歌が、国民のあいだで歌われていたが、実際の戦場は見るも無惨な様相をていして、歌にうたわれるような現状ではなかった、ということだった。
サイパン島を基地とした米空軍B29の本土空襲は、次第に熾烈の度を加えていた。
p72
爆弾や焼夷弾による猛襲は、日本の大都市を片っぱしから火の海と化し、壊滅させていった。特に、3月9日の夜から10日の未明にかけてのB29の東京絨緞爆撃は、歴史に残るすさまじいもので、私の住んでいた秩父の町からでも、東の空が真赤に燃えているのが見えたほどであった。
私はその真赤に燃える空を見ながら、集団疎開で町はずれの寺に、さびしさ悲しさをこらえて暮らしている子供たちも、あの空を眺めてこわがっているのではなかろうか、とふと思った。そう思った途端私は、くやし涙がはらはら落ちるのをおぼえた。
私はそのとき、こんなに日本の本土が空襲されて大被害を受けている、というのに、戦争は勝ちいくさだと報道されているが、ほんとうはどうなのだろうか、いくら戦時であるとはいえ、銃後の国民をこんなに苦しめて、戦争に勝つ気でいるのであろうか、と思った。
そんなせっぱ詰った、やり場のない思考力で戦っているのだから、日本はまったく勝利の道を歩むことなどできるものではなかったのである。
p73
若し負けたりしたら、誰がこの責任をとるのだろうか。私のような障害児は奴隷船の映画のように、ひどい目にあわされるのではなかろうか、などと真剣に考えたりもした。
紅蓮の炎の中を互に叫び、呼びかわしながら逃げ惑う人たちの姿を想像してみたが、それは想像以上のものであったようだ。当時、東京に住んでいて実際に体験した妻の話によれば、焼夷弾による火災からのがれるために、近くの川に飛びこみ、びしょぬれの毛布をかぶって、炎の中を逃げまわったが、その毛布がまたたくまに乾いてしまったということであった。
◇
私が高等科1年の3学期をむかえた、昭和20年(1945年)の1月、私たちの学年は昭和電工、東京チャック、それに学校農園のそれぞれの勤労隊の3班に強制的に分けられた。
私も久保も蓼沼、山沢もみな、学校農園勤労隊の仲間に属していた。農園勤労隊は主に農家出身の生徒が集められていた。私や久保、蓼沼、山沢は一人前の労働ができなかったので、主に家畜の世話をする役にまわされていた。
p74
山沢は、先天性の佝僂病体質で、脊椎が極度に前方に曲っていたので、力仕事は無理であったが、手先のきわめて器用な少年だったので、いろいろなところで無器用な私は助けられた。
寒い1、2月は、農園での労働はそれほどなかった。だから、もっぱらうすべり1枚敷いた床に腰をおろして、火の気の全くない教室を3つ取り払って、砂を詰める叺を大量につくる労働をしていた。
この叺は砂を詰めて、爆弾によって破壊された飛行場の滑走路の穴を埋めるのに、使われるのだということであった。ショベルカーやブルドーザーで短時間のうちに整地修復するアメリカに比較すれば、全く問題にはならない幼稚な方法である。それを知らない、日本政府、いや、たとえ知ってはいても、もう予算的にも科学的にも、どうすることもできないところまでいきづまっている現状であれば、こんな幼稚な方式をとるよりほかに方法はなかったのであろう。
物質的よりは、精神的なものを優位とした教育方針では、この方式をとることが、最もよい方法だったのだろう。
p75
とにかく私たちは約2ヵ月の間、夢中になってこの叺作りに全力を投じていたのである。
農耕労働に馴れない東京からの疎開組の生徒たちは、すべて軍需工場の方へ回されていた。旧制の中学校及び女学校の学生たちも、3年生以上はやはり昭和電工や、秩父セメント工場へ動員されたり、大野原に疎開していた被服廠の分工場で“神風“という文字を染め抜いた鉢巻きをし、朝から晩まで授業を放棄して、お国のために働いていたのだった。
また女学生の中には、挺身隊に動員され、通信に関する仕事にあたったり、航空機製作に関係した小工場で、部品の製作をしたりしているものもいた。そうした中で、小説『ひめゆりの塔』で書かれている、沖縄の女子学生の動員も、このころのことであった。
◇
縁故疎開の家族が、20年(1945年)の4月になると、この秩父の町にもずっと増えてきた。大きな広い屋敷や、幾部屋も備えている銘仙問屋の販売所には、何組もの家族が共同生活をしていた。
p76
それらの家族は大空襲で家を焼かれたので、知人を頼ってこの町へきた人たちであった。衣服は粗末なものを身につけ、顔も体も幾分栄養不足のためにやつれてはいたが、みな鼻筋の通った器量よしの人たちばかりだった。
13、4歳の少女が何人かいたが、みな美しい容姿を備えていた。いくら戦時下といっても、思春期の血潮が私の体内に流れていたから、やはりそうした美しい少女には自然、目をむけることがたびたびあった。時によってはそれらの少女たちに、私のできる範囲の親切をこころみたのであった。
私の親切というのは、食糧品を分けてやったり、木炭などの燃料をもっていってやることであった。
旅館を生業としている私の家でも、当時は家族と使用人が食べる米の量しか購入することができなかったので、“お泊りの方はお米を2合ご持参下さい”という貼り紙を、入口のガラス戸に貼らざるを得なかった。
学校農園の組の指導者は、40歳になったかならないかぐらいの年格好の五十嵐という教諭であった。
p77
五十嵐教諭は始終、肥桶を生徒にかつがせるので尿太という緯名がついていた。五十嵐教諭は、理論と経験の備わった有能な農業の指導者だったが、一旦怒ると岩石のような固い拳固を横っ面にとばしてくるので、生徒はみな恐ろしがっていた。
しかし教諭は、みんなで収穫した作物はまず労働したもので分けることを原則としていたので、私たちが分けられたものを収めるまでは、たとえ校長なり教頭なりがほしいと要求しても、決して分け与えるようなことはなかった。
そして私たちには無料であたえるが、自分をも含めて教師たちに配布するようなときは、必ず何がしかの労賃をとりたてていた。だから学校農園組の生徒たちは、労働がきつくても、五十嵐教諭にどんなに叱られ殴られても、また多少の陰口をきくことはあっても、作業をさぼるような者は一人もいなかった。
また五十嵐教諭は、授業時間の延長の場合には、別にどうということはなかったが、休暇中の作業のときは、必ず少額ではあったが、労賃をその生徒たちにあたえるか、労賃のないときは作物を配付して、それなりの労働の価値をみとめてくれた。
p78
教諭のこのやり方は、私が高等科の二年にすすみ、高等科一年との複式学級になってからも、決して変ることはなかった。
高等科2年になると、3つのグループはそのまま、進級となった。一年下級のものはそのまま、3つのグループの中に分け入れられることになっていた。一年下級のものの中にも私たちと同様、虚弱、病弱のものが二人ばかりいた。その二人は私たちの仲間に入り、虚弱、病弱組は、全部で六人となった。
五十嵐教諭は作業の合間に、人間の平等性について説いてきかせてくれた。そんなときにはいつも静かな口調で、
「人はそれぞれ頭脳の働きも、体の大きさも、力の強さも一定ではない。しかし、ある一定の仕事量までは共通してできる、といつも思っている。しかしそこから先はその人の持ち合わせた能力に応じてやらなければ、本当の仕事なり労働はできないものだ」
「お互いにその相手の力を認めない限り、本当に親しい仲間にはなれない。体格もすぐれ、力もある者はそれを誇って、弱い者を馬鹿にしてはならない。幾分、頭脳の働きに自信のあるものは、それを過信して労働を軽んじてはならない」
p79
「また体に障害があったり、虚弱病弱なものでも、決して自分を卑下してはならない。弱いものは弱いものなりに、精いっぱい仕事をしろ。障害や虚弱な体を理由にして労働をさぼったり、仮病をつかって怠けてはいけない。大自然は、その中に山があったり、谷があったり、樹木が繁茂しているから、美しいという感じを我々に与えてくれるのである」
「また、我々もそれ故にそう感ずるのではないか。それと同じで、みんながお互いに理解し合い、協力しあっている間は、素晴らしい仲間といえるのだ。だからみんなもお互いを大事にしながら、精いっぱい勝利の日までがんばって生き抜いていくんだ」
と話してくれた。
◇
ヨーロッパ大陸では、昭和18年(1943年)の2月に、スターリングラードでドイツ軍が壊滅し、9月にはイタリアが、連合軍に無条件降伏していた。
p80
だがドイツ軍は、新兵器流星弾を発明し、これを用いてロンドン市内を盛んに爆撃したりして、必死に低抗していた。しかし物量に物をいわせる連合軍は、次第に包囲を縮めていき、昭和20年(1945年)の3月に、ベルリンを攻撃、そして5月にベルリンは陥落し、とうとうドイツも連合軍に無条件降伏をした。
これでついに、昭和15年(1940年)に結んだ日独伊三国軍事同盟は全く消滅し、ひとり日本のみが連合軍と最後まで戦うことになったのである。
ところが、それよりすこし前の4月に、突然ソビエトより日ソの中立条約不延長の通告をうけた小磯内閣は、責任をとって総辞職をし、鈴木貫太郎内閣に政権をゆずった。
6月には激戦ののち沖縄戦が終結し、本土上陸作戦が計画されていた。昭和20年
(1945年)の7月に、米英中の三国は、対日共同宣言(ポツダム宣言)を発表した。
しかしこれに対して日本政府は、一応受諾したが、軍部の猛反対にあい、国民にその旨を通告することが、なかなかできなかったようである。
p81
そんな混乱の最中に、あのいまわしくも恐ろしい残忍極まる原子爆弾が、8月6日に広島へ、また9日には長崎へ投下されたのである。それに8日のソ連の対日宣戦布告を機として、とうとう昭和20年(1945年)8月15日正午の、天皇陛下の終戦の放送をもって、太平洋戦争は終結となったのである。
実際には、いつポツダム宣言を受諾したのか、しかと分らないが、若しそれが6日以前だとしたら、天皇をはじめ、当時の日本政府や軍部の犯した決断の責任は、重大なものである。また、日本政府のポツダム宣言受諾を公式に知っておりながら、もしくはその不徹底さのために知らずにもせよ、連合軍が投下した原爆のために殺傷された人々への責任は、連合軍が当然負わなければならない事実である。
だが原爆を投下させたアメリカ空軍はもちろん、それを指揮していた上層部は、昭和59年(1984年)の現在に至っても尚、責任をとろうともせず、原爆実験をなおも続けているのである。
まして終戦当時の大統領であった、トルーマンをはじめとし、現在のレーガン大統領に至るまでの各大統領は、みな反省の色もなく責任を回避し続けてきたのである。
p82
昭和59年(1984年)の現在でも、国際的にその反核運動が高まっているのに、民主国と自ら称するアメリカもソビエトも、原爆実験を決して禁止しようとはしていない。そして、宇宙に軍事衛星を打ち上げ、お互いにその状況を牽制し合っているのである。現在平和とはいいながら、なんとも不気味な平和が続いているとしか、いえない状態ではないか。
◇
昭和20年(1945年)の8月15日、その日はとてもよく晴れた、ものすごく暑い日であった。正午に重大な放送がある、というのでみんなラジオの前に坐って待っていた。ところが正午になっても私の家の並音の、おんぼろラジオでは、ガアガアと雑音がするばかりで、放送がいったいなにをいっているのか、その内容が全然ききとれなかった。
つまり、よくラジオやテレビドラマなどで、終戦の場面になると必ずもちいられる「耐へ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ忍ヒ」という、玉音放送の天皇の声が、殆んどききとれる状態ではなかったのである。
p83
しかしそのあとのNHKのアナウンサーの解説で、私は終戦を知り、日本が連合軍に敗北したことを知った。
ちょうどそのとき、父のところに集っていた父の仲間の一人は、いきなり、「そんな馬鹿なことがあるものか」と叫び、つづいて他の一人が、「畜生! 畜生!」
と叫んで、やたらと拳を振りまわした。
「なんのために俺たちは戦ってきたんだ、こんな放送をきくために戦ってきたんじゃねえ。こんなことなら、本土で決戦をすればよかったんだ」
ともう一人の男が鳴咽しながらいった。私はなんとなく息がつまるような思いで、思わず父の方を見た。父は何もいわず、じっとある一点を見据えていた。
ずっと以前、私がまだ小学校へも入らなかったころ、父は軍籍にありながら、思想活動をしたということで、軍法会議にかけられて、軍籍を剥奪されてしまったと聞く。
p84
そのとき父は若かったせいもあろうが、家中を日本刀をふりまわして暴れまわったという。その記憶が余りにも強烈だったので、父がまた、何かするのではないか、とふと思い、不安でならなかった。だが父は、いつまでもじっと坐ったままで一言も発せず、また身動き一つしなかった。
私はその場に居たたまれなくなって、一人ぶらりと外へ出た。そして自転車に乗って町へ行った。町には真夏の灼熱の太陽がぎらぎらと照りつけ、その熱でアスファルトの道路が溶け、ところどころがベトベトしていた。
町は人気がほとんどなかった。まるでそれは太陽にさらされた死の町のように、活気を失っていた。人々はみな終戦の放送をきき、家の中で種々の思いにふけっているに違いない。私はその静かな町を抜け、荒川の川原に行った。木陰に自転車を置くと、傷の一時ふさがった右足をむき出しにして、褌一つになると荒川の清流の中へ入っていった。
なぜそんな行動をとったのかよく分らないが、とにかく水の中へ身を沈めていった。
p85
10メートルも泳げないのに、私は渦の巻いている深いところまで手足をうごかした。渦は私の体を巻きこみ、何回も沈ませたり、回転させたりしたが、何回そうしても沈みっぱなしになるようなことはなく、私はいつの間にか、両足の届く浅瀬に押しやられていた。
水の中の私は、すこしも慌てず、またあせりもしなかった。恐怖というものが全くなかった。不思議だった。それは私にも分からない不可解なことであった。私はその不思議さを考えながら、川原の隅の木陰に横になり、大空を仰いだ。空はよく晴れ渡り、一片の雲もなかった。ただあるものは中天に輝くまぶしい太陽だけであった。
川原には私の乏しい視力の範囲でだが、全く人影は見られず萱のみあおあおとしげっていた。私は日本が負けたあとはいったいどうなるのか、といろいろ考えてみた。
つい最前、ラジオで聞いたポツダム宣言の解説の中で、日本国民を奴隷化しない、という部分が、妙に明朗な言葉になって残っていた。
p86
鬼畜米英がほんとうにそんな生やさしい仕打ちだけで満足するのであろうか、その場限りの出まかせないい分ではないのか……。
私はかつてみたことのあった「奴隷船」や「世界に告ぐ」という映画の中での、残酷極まる映像を瞼の裏に思い浮かべてみた。そして更にそうした奴隷にもなれない私のような障害を持っている者は、一体どんなあつかいを受け、どんな仕打ちをされるのであろうか、ということをいろいろ考えていた。
そう考えたとき、ある日、一人の教師に、それは冗談まじりだったが、
「お前のような片輪の奴は、奴隷にもなれやしねえ、だからまずみんな銃殺か毒殺だなあ、あるいはしばり首かもしれねえな」
といわれた無神経なことばを思い出した。
そのことばを思い浮かべたとき私は、自然に涙が流れるのをおぼえた。涙はあとからあとから溢れ出て、頬を伝わっていった。私はそんな顔を見られたくないので、両手で顔をおおって更に涙を流していた。
p87
それからどのくらい、そうしていたか分らないが、半ば半信半疑の状態におちこんでいたような私の顔の上の両手に、ふと手を重ねた者がいる。はっと我に返えり、両手を顔からはずし、その相手をみた。とそこには親友の一人である蓼沼二郎の、日に灼けた顔があった。
蓼沼はびっくりする私に向かって、
「お前もここに来ていたのか、やっぱりなあ」
といって、私の横に腰をおろした。私は泣顔を見られたかと思い、ややはにかみながら、
「うん、なんとなく来てしまったんだ、でもお前もだろうが」というと、蓼沼も首をたてに振って、
「そうなんだ、何か生きているのがいやになってしまってね」
と暗い表情をして、力のない声でいった。
蓼沼はさびしげにしばしあらぬ彼方を見ていた。ふとみると、蓼沼も褌一つのやせた裸だった。しばらくの間、障害と病弱な肉体を持ち合わせた二人は、目を閉じて黙していた。それから二人はお互いの身の上について、静かに語り合った。
p88
将来の、あるいはすぐ近日中にくるかも知れない、これからの自分たちの身の上を想像した。
二人は死ということについても語り合った。死ということについてまで語り合った二人だったが、話しているうちに心が落着いてきて、
「何も死を急いで求めることはないじゃないか。もうすこし情勢をみて、俺たちがどうしても生きられない世の中になったら、そのとき、死を選べばいいではないか。たとえ奴隷にもなれなかったとしても、生きる道はきっとどこかにある」という意見が一致し、二人は生きる気力を取り戻したのだった。
私も蓼沼も無意識のうちに、なんとなく死を求めてこの荒川へきたようであった。しかし二人とも話し合っているうちに死神に見はなされて、その目的を果せなかったとしか思えなかった。
すっかり気分が落着くと、二人は清流に体を沈め、水とたわむれ、30分ののちに自転車に乗って久保洋の家に行った。
p89
二人が荒川の川原で語り合ったことを話すと、久保はにっこり笑って、
「なるほどそうか、そうだな、何もあわてて死ぬことはない、死ぬときはいつでも死ねるんだからなあ。たとえ障害をもっていたって、病弱だって、お天道さまは平等に照らしてくれているじゃないか、お天道さまだって死ねといっちゃいねえぜ」
と満足げな顔をしながらいってくれたのだった。
久保がいった意味については、そのときはなんとなく分ったような気がして、ほっとしたのだったが、ずっとあとになって考えてみたとき、私はたしかに太陽は地球上の生物に対して、一日一回ある一定の時間、環境の多少の違いはあるにせよ、そのエネルギッシュな光と熱を平等に与えており、また生命あるものはみな、それを受ける権利を持っているのだと思った。
◇
戦争という気違いめいた現象は、そうした人間の尊厳とか生命保持に関する平等性を、一枚の赤紙と、天皇の命令という事象で、一人一人の生命を簡単になくさせるのである。そうしたとき命令をうけた者は、おそらく本意では死にたくないと思っても、命令には逆らえず、死ぬことがあたかも本意のようにふるまったのであろう。
p90
昭和20年(1945年)の6月の末に、私の家に泊った特別攻撃隊振武隊の隊員も、みな死を決意していた。本意でないにしても、死んでお国のために尽すのだ、という少年時代から培われた軍人思想教育は、特別攻撃隊に志願する、という決断をなさしめたのであった。
私はその隊員といろいろ語り合ったとき、陸軍と海軍が先陣争いをして武勲を立てることに汲汲とする余り、最後には全く非協力的であるという事実を、知らされたのである。
生命をすてる覚悟でいる航空兵が、陸海軍ともに相手をけなし合っていたのでは、とてもこの大戦争を勝利に導くことはむずかしい、とふと子ども心に思ったものであった。だが、そのときは、まだ実際に負けるとは思っていなかったので、そんなことはない、と私は心の中で強く打ち消したのであった。
◇
p91
久保の家からわが家へ帰ると、玄関先の松の木は、いつもに変らぬ姿で私を迎えてくれた。帳場のある座敷には、父、母、兄嫁と二人の姉、それから四、五人の使用人が集って、広い座卓のまわりを取り囲んで坐っていた。卓上には茶道具が置かれてあった。
帰ったばかりの私が父のとなりに坐ると、父はそれを待っていたかのように、落着いた口調で口を開いた。
「みんなも、ラジオの放送や人の話を聞いて知っているだろうが、日本は今日、連合軍に負けたんだよ。でも戦争には負けたが、国がなくなったわけではないし、日本人がいなくなったわけでもない。これからはみんなで力を合わせて平和な日本を築くために、もう一度がんばるんだ」
「とにかく今日から夜ぐっすり眠れるし、これからは燈火管制もない。なぜってもう空襲のサイレンの鳴ることはないんだからなあ。ほんとにこれまで皆よくやってくれたね、私は心からお礼をいいたい。ほんとにご苦労さんだったな、今日はゆっくりお茶でも飲んで、のんびりやってくれ。明日からのことは、また明日、考えればいいからなあ」
p92
父はそう話し終ると、ゆっくりと一人一人の顔を見、微笑みかけながら、それから、つと立ってふらりと外へ出ていった。空襲とか、燈火管制といった言葉はもう必要ではなくなったのである。私はこの言葉を思い出すたびに、ある日のいまわしい記憶がよみ返っててくるのだった。
◇
私の住んでいた秩父町は、関東西部という地域に位置していた。サイパン島から富士山を目標に飛んできたB29は右に旋回すると、ちょうど秩父の上空を、東京の空に向かって飛んでいく。即ち、関東西部はB29の通り道だったのである。
恐ろしい不気味な重くるしい爆音が、毎夜のように頭上を通過していった。水戸沖からの艦砲射撃がドドドッ、ドドドッと夜の山に響きわたった。
昭和19年(1944年)の晩秋のころから、神風特別攻撃隊という特殊な部隊が、志願兵によって編成され、つぎつぎとその兵士たちは、陸海軍とも戦闘機に護衛され、死出の旅路へと飛び立っていったのだった。
p93
死ぬことを当然のように指導し、それを信じさせる教育がいかに恐ろしいものであるか、私は今しみじみと考えさせられるが、当時の10代の少年たちは、それを心の底からよろこぶように、叩き込まれていたので、特別攻撃隊にあえて志願するものが出てきたのである。
私の町からも、加藤和三郎という勇士が、陸軍の勤王隊という特攻隊に参加していた。その出撃の様子がニュース映画として放映され、加藤はその中で4回も大写しになって、勇ましい姿を見せていた。
特攻隊には、必ずしも飛行機ばかりでなく、人間魚雷というのがあって、いずれも敵艦に体当り攻撃をするという、いわゆる人間兵器もあったのである。特攻隊に属した兵士の綴った書簡を読むと、みないちように御国のために命を捧げる、といったことが書いてはあるが、どこかになんともいいようのない、悲痛なこころが、にじみ出ているように思う。
私はそんな少年のいじらしい心の奥に秘められた声なき声を感ずるとき、たまらなくなり、どうして特攻隊がいかなければならないんだ、それほどにしなければ、日本は勝てないのか、と真剣に考えたものである。
p94
このような特攻隊の犠牲にもかかわらず、不沈艦といわれた戦艦大和も、沖縄沖で撃沈され、日本の連合艦隊は完全に壊滅したのだった。
◇
昼間の空襲はときどき、この田舎町にも爆弾や焼夷弾を落し、多数の死傷者を出した。私が通院していた柏崎外科医院にも、何人かの負傷者が頭に白い包帯を巻いて、待合室にすわっていたのを、今でもはっきりと記憶している。
神風が吹いて日本は勝つんだ、そんな言葉が盛んにささやかれ、本土決戦に備えて竹槍の稽古が必死に行われたり、地上に目と耳をふさいで伏せる、爆弾投下時の訓練なども盛んに行なわれた。
しかし火焔放射器と竹槍では、とうてい勝負にはならない。だからこの事実を知らされていない私たち銃後の国民は、ただただ神風を信じ、天運を信じて何もかも我慢に我慢を重ねていたのである。
とうてい役にたたないような、松の根からとる油、いわゆる松根油をとるために、必死になって松の木の根方を掘っている人もいた。
p95
その当時の国民は全く信じられないほどの倹約と努力を重ね、勝つためにお国のために、耐えて頑張っていたのであった。
◇
終戦の日の翌日、即ち8月16日、私は家畜の世話もあったので、朝早く学校へ行った。その日が特別召集日だということは、前の日の夜、すでに知らされていた。朝礼で校長が、日本が連合国に無条件降伏し、長い間、苦痛であった太平洋戦争が終結したことを告げた。そして最後に、これから、いや今から日本の再建と、世界の平和のために努力していこう、という訓話があった。
私は、話をしている校長の顔をじっとみていたが、その顔にも目にも憂いの影は見られなかった。それは全く義務的な単なる挨拶のようにしか思えなかった。私はいい知れぬ憤りのようなものを感じ、身のふるえるのをおぼえた。
教室に入るとみな、しんと静かにしているので、私も心をしずめて自分の席に着いた。いつも威張りくさって暴力をふるったりする嫌な奴らも、さすがに今日は首うなだれてじっとうつむいて、みな憂いに満ちた暗い表情をしている。
p96
担任の五十嵐教諭が、満面沈痛な表情で教室に入ってきた。教諭はいろいろ話をしたあとで、一瞬声をつまらせると、
「君たちのような純粋な少年たちを、今日までだましてきたような結果になって、ほんとうに悪かった。私だって勝つと思って頑張ってきたのに、嘘をついてほんとうにすまなかった」
といい、ハンカチを取り出すと、顔をおおってしまった。そして滂沱とばかり流れる涙に鳴咽をもらしていた。
たちまち教室中に鳴咽やすすり泣きの声が広まっていった。私もたまらなくなって、手拭を目にあてた。久保も蓼沼も山沢も、それからいやな奴らも、このときばかりはみな心から泣いていた。それは日本の敗北を悲しんでのことや、将来の不安を思いながらのことでもあったのであろう。しかしそれよりも、尿太という緯名をもって、鬼のように恐れられていた五十嵐教諭が、まったく純朴な人間性にみちた人格者であったことに感動して、みんなが泣いたというのが真実だったのである。
p97
私は久保、蓼沼、山沢といっしょに、松葉杖にもたれながら校門を出た。空はあくまでも青く晴れわたり、真夏の陽の下にひまわりが輝いていた。
立秋はとうに過ぎたのに、その年はなかなか涼風が吹いてこなかった。四人は仲よくお互いをいたわり合いながら、町なかを歩いていった。私はそんなときふと、四人がお互いを罵倒し合ったある日のことを思い出した。
よく考えてみれば、それは他愛もないことであったが、お互い障害や病弱の肉体をもっていると、少年なるが故にそれを必要以上に重く意識し、他のものをうらやみ、また他の者より先んじて作業に励み、ほめられようとしたり、他の健康な級友からも軽蔑されないように努力したりした。
またいかにも親切なことをいいながら、その実、他のものを作業に出させないようにし、自分だけがいい格好をしようとしたりしたのである。
だが、そんな浅はかなもくろみはすぐに露見してしまうから、たまにはそれがお互いに爆発して大喧嘩になり、口汚くののしり合うようなことが、弱さゆえにあったのである。
p98
そんなときには必ず、四人のうちの一人か二人は心も体も疲れ果て、けっきょく作業を休むことになったりして、お互いが悲しい思いにさせられたのであった。
その日も何かの誤解で家畜の世話などそっちのけにして、激しく猛烈にののしり合っていた。ところが、そうしていたとき、突然、空襲警報のサイレンが鳴り、それといっしょに飛行機の爆音がきこえてきた。
はっとしてその方を見ると、アメリカのグラマンF6が三機、こちらを向いて飛んでくる。
「おい、敵機だ、危いっ、壕へ入れ!」
という蓼沼の声に四人は必死になって壕へ急いだ。
久保が私の手をとり、蓼沼が山沢を背負って壕の入口まで走った。私は松葉杖を放り出して必死にびっこをひきながら走った。ダダ! ダダッ! ダダダッ!とばかり、機銃が頭上ですさまじい音を立てて、ひっきりなしに鳴りひびき、すぐ耳の側をヒュウー、ヒユーと弾が風を切って通りすぎていった。私は目がくらむようだった。
p99
夢中で防空壕へころげ込んだあとでも、まだ機銃の音はなかなか鳴りやまなかった。壕の入口から差し込む光に照らされた三人の顔は、真っ青だった。恐らくこの三人も私同様、心臓の鼓動が激しくなっていたにちがいない。
四人はお互い顔を見合わせながら、
「よかった、よかった、危なかった。そうだもうすこしとび込むのが遅かったら、みんな一ぺんに揃って地獄いきだったなあ。あのままずっと喧嘩などしていたら、恐らく四人とも命はなかったんだぜ」と口ぐちに興奮した口調で、早口にいい合った。
しばらくたつと、艦載機の爆音と、せせこましい機銃の音が聞こえなくなり、やがて空襲警報解除のサイレンが鳴った。四人はほっとして、壕の階段をのぼり地上に出た。周囲を見渡しても特に際立った変化はなかった。
私の松葉杖が入口から5メートルぐらいのところに投げ出されてあった。この恐ろしい体験以後、四人はお互い真からの友となり、一度も争うようなこともなく、なぐさめ励まし助け合うようになった。
p100
九死に一生を得た仲間同志が、お互いの命と心を大切にするために、固く結ばれたのである。
17日の午後、四人の親友は、久保洋の家に集まった。私たちは久保の母親の作ってくれたぶっかき氷をかみ、生胡瓜をつまみながらいろいろな話をした。そのうちに久保がゆっくりとした口調で、次のような話をはじめた。
「今だからもう何をいってもかまわないだろうが、俺はこんどというか、昭和6年以後の一連の戦争は、勝ち目の少ない無駄な戦争のように思えてならなかった。負けたからいうわけではないが、俺はどうも国民をこんなに苦しめる戦争がほんとうに勝てるのか、と思ったよ」
「まずこんなことでは、たとえもし勝ったとしても、またすぐに逆襲され負けてしまうと思ったが、なぜって、応援している銃後の国民に力がなくなったら、戦争は勝ち目がないからね。それに俺は親父の知合いから紹介された人に、ときどきこんどの戦争に関する真相に近い資料を見せてもらっていたんだ」
「幸い俺は、親父が死ぬ前に、英語の読み書きを学び、会話も勉強していたんで、親父が死んだころには、ごく普通の文章なら読み書きができるところまでになっていたんだ。
p101
だからその人からときどき見せてもらえる英語文の資料もどうにか読むことができたんだ」 「それから親父がどこで手に入れたのか分らないが、小さな無線器を持っていたので、それでアメリカのニュースや、情報をキャッチすることができたんだ。ちょっとスパイもどきのような気がして気がひけたが、じっと耐えて資料をよみ、情報をきいていたんだよ。でも聞きたいことがあっても、その無線器を使って電波を出すことはできなかった。なぜって、一度でも電波を出せば、すぐに特高警察からねらわれるからね」
「まあそれはどうでもいいけど、それらの資料を整理してみると、とても日本は勝ち目がないことがよく分ったんだ。だって余りに大本営が虚偽の報道を大戦果として、ラジオから国民に流し、決して真面目に真相を明かそうとはしなかったからね。ところが、アメリカはちゃんと真相に近いと思われる報道を国民にして、戦闘意欲を注いでいるんだ。要は人間の器がちがっていたんだなあ」
久保はここまで話すとひと息ついて、解けかかった氷水をのみ、胡瓜をつまんでうまそうにぽりぽりと音をさせながら、更に話をつづけた。
p102
「戦争を単なる精神力や観念論で片づけようとした狂信者が、日本政府や軍部の中で、わがもの顔に振まっていろいろと妄想し、指図していたから、誇大妄想が戦争という名のもとで、世界平和とか、大東亜共栄圏とかいう形になって現われたんだ」
「しかしもともと日本は物資がないから、早いうちに南方の石油のたくさんとれる島をあわてて攻め、占領したんだよ。俺はこの戦争をシンガポールを陥落させたところで止めれば、まあ日本はそう損失がなかったのではないかと思うね。だが、狂信者の集りの東条内閣は、力もないのに馬鹿な欲をかいたんだなあ。思い上りが、更に妄想を拡大させたんだよ」
「いっぺん嘘の報道をしたら、ほんとうの報道なんかできないからね。それからはずっと終戦のその日まで、虚偽の報道をしていたんだ。しかも連合軍に暗号の解読をされていることも知らないでね。狂信者は勝手にはじめたんだからいいが、銃後の国民や下級の兵隊たちは、ほんとに馬鹿をみた戦争だったんだ」
p103
久保は最後のところは、ため息まじりで半ば吐きすてるようにいっていたが、私たち三人はこの驚くべき久保の、整然とした話をきき、ただうなずくばかりであった。
確かにいわれてみれば、満洲事変のころから調子はよかったが、得体の知れない、なかなか終りそうもない戦争だとは思っていた。がしかし、久保がこれほどのことを知っているとは思わなかった。私はすっかり久保の偉さに敬服し、更に話をつづけるようにすすめた。
すると久保は、ちょっと恥かしそうにてれ笑いをしながら、
「じゃあ、もうすこし話させてもらうよ」
といって更にことばをつづけた。
「日本軍にも割に科学を重んずる、いい将軍はいないでもなかったけど、その科学性はいつも最後には、狂信者の妄想観念と、時代おくれの経験主義によって、あえなくも握りつぶされてしまったんだ」
「だから銃後の庶民の研究もその科学性については、たとえ素晴らしい発見や発明があっても、それを時の政府や軍部は受け入れなかったんだよ。
p104
受け入れない一つの理由は、それに使う予算がなかったこともあったが、もっと大きな理由を想像すれば、政府も軍部も無能さを国民の前にさらけ出すことに、恐れを感じていたのだと思うよ」
「だからそういうものはすべて排除し、神風説のような妄想的な全く当てにならない観念論を、まことしやかに信じ、また国民にも信じさせるように盛んに宣伝して、武士道とか称して、精神中心主義を学校教育を通して、少年少女たちに植えつける努力を計ったのだよ」
「でも、これはある意味では成功したんだね。だが、ミッドウェー、ソロモンなどの海戦で、科学的にも物量の上でも、劣っていることを知らされながらも、まだ無駄に体当り主義をもって特攻兵を平気で殺すことの、無神経さをつづけていたのだ。だから、まさに普通の精神を持ったものの考えることではないね。そうなればやはり俺は、狂信者と呼ばざるを得なくなるんだ。結局こんどの戦争は、狂信者の支配する国と、科学性を重んずる国との戦争ということになってしまったんだね。
p105
悲しいけれども、俺にはそうとしか思えないんだ」
そこまで話すと久保はつと立って、厠へ用足しに行った。そのうしろ姿を目で追いながら、蓼沼が、山沢と私に向かって、
「しかしあいつはよく、いろいろなことを知っているな、どこで?むのか分らないが、全く驚いたなあ。でもその無線器というのを見たいもんだね」
といった。すると機械好きの山沢が、
「そうだな、その無線器ってやつを、俺も見たいもんだな。でも英語しか聞こえないんじゃ、俺には雑音が聞こえるのと同じだよ」といって笑った。
蓼沼と山沢は機械いじりや工作が大好きで、二人とも模型飛行機やグライダー作りの名人だった。二人とも県の大会で、3年つづけて入賞している猛者だったのである。
私は二人の話をききながら、厠から戻ってきた久保が、さっきの席に坐るのを待って質問した。
p106
「お前の話を聞いていると、どうも日本の方が悪くて負けてうれしかったみたいだけど、じゃあなぜ昨日は、あんなに涙なんかこぼして泣いたんだよ、まさか変なことをいうが、空涙じゃないんだろうね」
というと、久保はちょっと表情を変えたが、
「そりゃあ俺だって日本人だから、負けたことはくやしいし、また悲しい。だから嘘偽りなく涙を流して泣いたんだよ。しかし日本がよいか悪いかということになれば、公平にみてとると、先に侵略を開始したのは日本軍の方だからね。それは満洲事変だって支那事変のときだって、またこんどの大東亜戦争だってそうではないか。しかもそれを自分の方から仕掛けておきながら、相手を悪くいつてるんだから、どうしても日本の方が悪いというほかはないよ」
と苦笑しながら平然と答えた。
つい二日前に日本が負けたことを知らされた久保以外の三人には、ちょっと学が違うという感じで、久保の話を半信半疑でただ唖然として聞くほかはなかった。
だが前々から歴史についてもかなり深く書物を読んでいた久保には、それだけの納得できる一連の史実を熟知していたにちがいない。
p107
久保はとにかく優秀な生徒だった。心臓がわるいために、中学校を不合格にさせられたが、不合格にした中学校は、大へんな損失をしたものだと思いたいくらいだ。なぜかといえば、その当時の久保は、高等科二年に在学していながら、旧制高校の一年程度の実力を持っていた。英語はとくに抜群で、ドイツ語も数学も強かった。
蓼沼も理科と数学には秀いでていて、特に機械工学については、優秀な頭脳のひらめきをみせていた。
電気機械いじりに興味を持っている山沢が、ふと思い出したように、
「おい久保、その無線器というのを俺たちに見せてくれないか」
といった。久保は首を横に振りながら、
「悪い悪い、今はないんだ、特高警察にかぎつけられては困るから、資料の提供者にこっそり預ってもらっているんだ」とすまなさそうに、
「今度、近いうちにきっと取り戻しておくから、それまでちょっと待ってくれ」と何度もいった。
p108
すべての資料は無線器と共にその提供者に預けたのであろうが、私はその後、いち度もその無線器を見ることはなかった。
私と蓼沼と山沢の三人は、夕方、久保の母親にあいさつし帰路についた。久保は私たちを送りながら町角まできて、
「これからはみんなで文学書を勉強しようじゃないか、そしてもっと人間性を研究しようよ」
と、にこにこしながらいって手をあげた。
私はみんなと別れて一人帰りの道を急いだ。歩きながら、今きいたばかりの久保の話を反芻してみた。それが実によくまとまっているのに驚かされた。それは、14歳の少年の頭脳でまとめられたものとは、とても思えなかった。私は久保の頭脳の優秀なのに、あらためて驚嘆した。そして、いい友人をもったなあ、としみじみ思ったのである。
ところがなんということであろう、私はそれから僅か一年半もたたぬうちに、この3人の友を失ってしまったのである。
p109
山沢は心臓麻痺で、蓼沼は結核症、久保は心臓弁膜症の発作によって、それぞれ不帰の客となったのであった。
ただひとつ不思議に思えてならないのは、久保洋が持っていたという、電話方式の小型無線器が、小さなアンテナ1本で敵国の情報が傍受できるなんて、そんな性能のよいものが実際にあの当時にあったかどうか、ということである。
しかし、久保洋の亡くなった今となっては、それを確かめることはできない。
現在アマチュア無線の免許をもっている私には不可解なことである。
8月30日に、マッカーサー元帥は日本本土に到着し、9月2日、東京湾頭のアメリカ軍艦ミズリー号上で、連合国側の降伏条件に対する日本全権との、正式調印が行なわれたのであった。
それから二週間ほどたったころ、私の家に米国陸軍写真班のスタッフ6名が、ほぼ二週間投宿した。彼らは日本の田舎の生活をカメラに収める仕事をしていた。
彼らは紳士だったが、最初の3日間は腰から剣銃をはずすことはなかった。
それから間もなく、100名ほどの米兵が秩父の町に進駐した。
p110
最初のうちはこの田舎町の住民は彼らを遠巻きにして、物珍らしげにうわさし合っていたが、しだいに彼らと親しくなるようになり、派手なワンピースを着た若い娘が、米兵と腕を組んで歩いている姿もまれではなくなった。こうして秩父の町はようやく落着きをみせてきた。
10月の中ごろ、私は父に連れられて東京へ行ってみた。ところが東京まで行かないうちに、全く焦土と化した熊谷市の姿をみて、私は唖然とした。熊谷市は不運にも、終戦日の前夜に米空軍の焼夷弾攻撃をうけたのだった。
東京のやられ方は更にすさまじかった。省線に乗って眺めた東京の町は、まるっきり場所の見当が掴めなかった。全くそれは死の大都会というほかなかったのである。
私は父と上野公園に行き、昼めしにと持ってきた母の作ってくれた握りめしを出して食べようとした。するとその握りめしはあっという間に、そこにいた浮浪児たちに盗られてしまった。私がはっとして父を見ると、父は笑って、
「お前は家に帰れば食えるんだから我慢しろ」といい、まだ残っていたむすびを浮浪児たちに全部分け与えてしまった。
p111
「彼らだって好きこのんで浮浪児になったわけではない、すべてが戦争のためになったんだ。だからかわいそうなんだ。持っているものが、持っていないものに当然分け与えるということが、平等性を生む原則なんだ。お前は家に帰ればどんなものでも、どうにか食べられるではないか、だから持っているものは分けられる範囲で分け与えるのがいいのだ」
と父は私をさとした。
ガードの入口のところに、靴みがきの少年がいた。父と私がそこで靴を磨いてもらっていると、ピンク色のワンピースを着て、唇を真っ赤に塗った若い日本女性を乗せた、アメリカ兵の運転するジープが、すさまじい音をたてながら、すぐ側を通り抜けていった。
あの、宮域まり子のガード下の靴みがき、という歌をきくと、今でもそのときの様子が思い浮かぶのである。
新橋から銀座に抜ける道を歩いていると、安全地帯にたくさんのさつまいもの蔓が這っているのを見て私は驚いた。
p112
そのとき頭上を轟音を立てて、銀色にひかる。B29が、青空を背景に悠然と飛んでいるのをみて、あらためて日本は負けたんだなあ、ということを思い知らされたのであった。
リンゴの歌が、戦争の暗い沈みがちな世相のなかで、町のあちこちに明るい歌声を投げかけたということは、あるいち面では事実であろうが、しかしあの東京の街をながめた経験をもつ私は、正直、日本はこれからどうなるのだろう、と真剣に考えたものだ。
だが現在の東京の街は、今や世界に誇る大都会になっている。私は時おり思う。いったい東京の何がそんなに誇りに感じられるのであろうかと…。そこには、昭和20年(1945年)にうけた大空襲など、とうに忘れられてしまったのではないか、とさえ思えて、なんともいいようのない空しさをおぼえるのである。
◇
一昨年、特にクローズアップされて問題になった、文部省教科書検定にかかわる問題をみても、何か釈然としないところがあるが、あれは誰がなんといおうとも、かつての日本軍が旧満洲や、支那の大陸で行なってきたことは、まぎれもなく侵略であり、決して、進出とか侵攻といった生やさしい表現で片づけられるものではない。
p113
私が小学校時代に学んできた歴史や教育は、その当時は間違いなどとは決して思わなかったが、あやまりであれば、一日も早く、真実にもとづいた歴史や教育の見方で、考えなおすべきだと思う。
しかし一旦、若い年代に植えつけられた、強烈な思想教育は容易に変えられるものではない。だから教育というものは、その面からも実に大きな責任がある、ということを、終りにあたって私は声を大にして、強く言いたい。
そして現代社会の中では、弱い立場といわれている老人や障害者、病弱者などでも、安心して生活できる、そんな平和な社会が、一日も早く、おとずれるよう祈りながら、それに向かって私なりに努力をしていきたい。
少年時代の夜祭りとサーカス・・・p114
p114
私の生まれた秩父の町は、昔から織物の銘仙と、セメント、木材の三大産物の町として知られているが、もう一つ関東一円に名高い秩父夜祭りがある。
いまの秩父の夜祭りは、やたらと観光的ではでやかな写真入りのパンフレットなどで宣伝されているが、私がまだ小学校の低学年のころは、そんなに宣伝に力を入れなくても、近郷近在からたくさんの人びとが、おどろくほど集ってきたものであった。
当時、秩父の人は、この秩父妙見さまの夜祭りのことを、冬の祭り、または大人の祭りとも呼んでいた。その期間中に絹の大市が開かれ、全国から絹商人が買付のために集まってきたという。田舎びたなかにも、じつに、はでやかな誇り高い祭りであった。
p115
祭りは12月の1日から6日までつづき、千軒余りの露店が祭りの間中、町の大通りの両側にずらりと並んで、賑やかであった。
名物の6台の山車は、2日と3日だけしか動かなかったが、祭りは六日町といわれる6日の日までつづいて賑わった。なかでも御山まいりといって、3日の夜、6台の山車が秩父公園のそばにある団子坂という、かなり急な坂道をのぼるのがいちばんの見ものであった。
その当時の町の主な通りには、道の両側に紅白の柱が2メートルほどの間隔で立てられ、その柱の2メートルほどの高さに、紅白の横板をうちつけ、そこに紅白の幕を張り、各柱の上には大きな祭提燈がとりつけられてあった。
この紅白の柱は祭りの10日ほど前から立てられたのであったが、柱が立つと、町中に祭り近しの気分がみなぎっていった。
秩父公園には、そのころからサーカスの小屋がけがはじまっていた。私は学校から帰ると、かばんを家のなかへ放り投げ、すぐに祭り好きの3、4人の友だちといっしょに、サーカス小屋のそばの檻に入れられている動物を、見にいったものである。
p116
檻の動物の見物は、余り動物園などにいったことのない、この田舎町の少年少女たちには、またとない絶好のうれしい機会であった。
檻の中にはオランウータン、日本猿、カンガルー、オットセイ、山犬、日本熊、豹、虎、ライオンなどがいた。象だけは檻の中ではなく、周囲を柵でかこわれた大木の幹に、太いくさりでつながれていた。私は毎日のように秩父公園にいき、この動物たちをながめて、夕方暗くなるまで遊んでいた。
私はそこでまた、動物ばかりでなく、不思議な格好の、大きなネクタイをしめた若い女や、だぶだぶのズボンをはいた、子どものように背の低いひげもじゃの男が、忙しげに働いているのをみた。その奇妙な人たちはみな、サーカスに関係のある人たちのようであった。どの人たちも余りいい顔色ではなく、疲れてやつれたような顔つきをしていた。
小屋がけをしている周囲には、4、5軒の屋台が食べものの店を出しており、そこで焼きそばや、キャベツボール、お好み焼などを売っていた。
p117
私は友だちといっしょに一銭銅貨をだして、それらを買って食べたが、どれも忘れられないよい味であった。
◇
サーカスは12月1日から昼夜2回、興行された。昼の部は12時から夕方の5時まで、夜の部は5時半から深夜近い11時までで、夜の部の方が30分長かった。
私は柴田サーカスとか、早川サーカス団の曲芸や軽業を見たが、どれも忘れられないすばらしい思い出として残っている。柴田サーカスの特別寄びものの空中ブランコ“火星の運河”は、はらはらさせられる、すごい早業でとんぼ返りをしながら、ぶらんこからぶらんこへとび移るというものであった。それは見るものの手に汗を握らせ、その格好よさに思わず感動の叫びをあげさせた。
動物たちの演技もなかなかのもので、燃え盛る火の輪をくぐる豹、象の碁盤乗り、オットセイの毬つき、オランウータンのオートバイ乗り、カンガルーのキックボクシング、6頭のライオンの合同曲芸など、どれを見てもこころがおどったものであった。
p118
なかでも私がいちばん興味をもって、手に汗をにぎりながらながめたのは、24、5歳の若い娘と、大きな虎との格闘競技であった。虎はすさまじいうなり声をあげながら、娘にとびかかっていった。娘と虎はごろごろと舞台の上をころげまわって、はらはらさせられたが、それでも最後に、娘が虎の背中に馬乗りになって押えつけ、その格闘はおわりとなったのである。それは最後まで胸をどきどきさせる、恐ろしい競技であった。
サーカス小屋のほかに、お化け屋敷や地獄風景、オートバイの曲芸などを見せる小屋もあり、どれもみな面白いものであった。
私が腓骨骨髄炎で外科医院に通院していたころ、ある日、サーカスの少年と偶然知りあうことがあった。私はその少年に、自分もサーカスヘのあこがれのようなものを持っている、と話したことがある。するとその少年は静かな声で、サーカスの暮らしは連日がつらいものであること、曲芸の訓練がきびしく、指がひょうそうで化膿しても休ませてもらえず、泣いても誰もいたわってはくれないこと、また大人が信じられないことや、ほんとはいつまでもこんな生活をしていたくないことなどを、話してくれた。
p119
昭和18年(1943年)の10月になると、軍部を中心とした政府の命令で、動物園やサーカスなどで飼われている猛獣は、全部殺されてしまったから、それ以後は、猛獣たちのいないサーカスを見ることになったのである。
それは日本本土が、米空軍に爆撃されたときにおこる、大混乱のための処置であるということはわかっていたが、私はなんとなく意味もわからず殺される猛獣たちが、哀れにおもえてならなかった。
◇
旅館を生業としていた私の家は、夜祭りがくると大忙しであった。私の母などは、嫁いでこの方、夜祭りを落着いてみたことがないといっていた。
12月1日には、旅館の部屋はすでに満員となっていた。3日の夜になると、客たちのなかには廊下にまで敷きつめた布団の上に、洋服のまま寝て朝をむかえる人もいた。また旅館に泊ることのできなかった人たちは、映画館がはねるのを待って、その客席の畳のうえに横になり朝をむかえたりしていた。
p120
特に目立ったことは、千軒あまりの出店を出す香具師が、1日の午後、秩父駅前で極東組の親分をでむかえたあと、店を出す場所の割り振りをするために、群がっていたことである。だからその日からは町中に目つきのよくない、やくざ風の男が何人も連れだって、肩で風を切ってぶらりぶらりと歩いているのを、よく見かけたものである。
◇
さていよいよ山車のことになるが、2日、3日の昼間に引かれる山車は、町筋で止まるとさっと舞台に早変りする。そこで娘たちの踊りが、三味線や笛、太鼓、鼓に合わせて披露される。
金糸銀糸の縫取の豪華な緞帳が、拍子木の音で上げおろしされ、山車は100メートルほどすすむと止って、そこでまた踊りが披露される、という形式になっていたのである。
p121
山車が止って、娘の踊りが披露されるときには、秩父の町の大通りは人びとで、まさにすし詰の状態になっていた。町中は屋台囃のすさまじい音響や、威勢のいい香具師の掛声、群集のごったがえす音などで大変な賑わいであった。
夜になると紅白の柱の上に取りつけられた祭提燈に灯がともり、山車の周囲に飾りつけられたぼんぼりにも灯が点され、その美しさはひと際きわだって人目を魅いたものである。
秩父屋台囃の大太鼓は、打ち寄せる大波のごとく、小太鼓は岸辺のさざ波のごとく、また鉦の音は、岩場にはねかえる波のしぶきを表し、笛は磯千鳥の鳴き声を表現するというもので、実に豪壮な囃である。
6台の山車は、その夜、秩父神社に集合してから1台ずつ順に、秩父の目抜き通りを通過し、東町通りへ曲り、黒山のような人だかりの中を、秩父公園の団子坂へと向かっていくのである。
秩父の夜祭りのクライマックスは、お山参りといって、この6台の山車が1台ずつかなり勾配のきつい団子坂を、いかにのぼるか、のぼりきるか、ということであったようだ。
p122
このときは、山車に取付けられた太い曳き綱のほかに、補助綱を左右一本ずつつけて、計4本の綱で大勢の人が引っぱりあげる。山車の大きな車がゴトゴト、柱はギシギシ、山車に乗っている4人の囃手は、精いっぱいの声ではやしたて、秩父屋台囃はまさに最高潮であった。
こうして坂をのぼり切った山車はひと休みし、お山参りをすませ、そこで仕掛け花火を観覧し、こんどは団子坂をくだるのである。登るときよりもこの下山のときの方がずっと、危険性が多いということであった。
秩父夜祭りの名物のひとつである仕掛花火は、独特な大きな破裂音をあげ、空いっぱいに優雅な美の世界を、次から次へと展開していった。
仕掛花火が終ったあと、サーカス小屋からジンタのクラリネットが、切ない音色できこえてきたのも、とても印象的であった。とくに3日の日には昼夜をわかたず、町の中には20万人以上の人びとがごった返していたのであるが、私はその雑沓の中を友だちといっしょに、歩きまわっていた。
p123
そんななかで私はとくに、紅白の柱や、紅白の幕、とりつけられた祭提燈や、色彩豊かな山車の彫物や緞帳、それからサーカス小屋の前に吊されている各種の優勝旗の色調を眺めるのが、大へんすきであった。私はそのなかのいくつかをスケッチしたり、絵筆をもって描いてたのしんだりしていた。
しかしそんな私でも、ごく幼いころは、人攫いにさらわれるといって驚かされたので、一人で町の中を歩くようなことはなかった。人攫いにさらわれた子どもはみな、サーカスに売られて連れ去られてしまうのだ、ということを聞いていたからである。
◇
6台の山車が町中を引きまわされる秩父夜祭りも、昭和17年(1942年)が最後であった。昭和18年(1943年)からは、戦時下では華美な祭りはまかりならんということで、祭りはすべて山車のない祭りとなった。集ってくる人びとは、男は国民服、女はもんぺ姿というのが多くなり、なんとなく祭り気分がうすらぎ、あの紅白の柱は、その年から立てられなくなった。
その後、昭和19年(1944年)になると、祭りの規模はぐんと縮小され、あの紅白の柱はとうとう、防空壕を作るときの資材としてつかわれてしまったのである。
p124
ふたたび山車が町にあらわれ、夜祭りをむかえることができたのは、終戦の年の昭和
20年(1945年)の12月の祭りからである。しかしその年は本町の山車1台が出ただけで、ほかの町内の山車は出されなかった。この山車も町のなかを引きまわすということはなく、ただ本町の町角に飾りもののように置かれただけであった。
しかしたった1台の、飾りもののような山車が出されただけであっても、集る人の数はぐんと増えて、人口3万そこそこの小さな秩父の町に、10万以上の人が集まったのである。目抜き通りの両側には、それでも200軒ぐらいの出店が並んだりして、かなりの賑わいをみせていたのであった。
私はその年から屋台囃の練習をはじめた。実際に6台の山車が揃って動いたのは、昭和22年(1947年)の冬からであった。私は昭和23年(1948年)の秋に失明したのであるから、6台の山車の揃った夜祭りを見たのは、この年が最後であった。
失明して夜祭りをみることはできなかったが、屋台囃の係として山車にのることができたので、夜祭りのたのしさを、鉦や太鼓、笛などの音色による感覚で満足することができたのである。
戦時対策として動物が殺され、昭和18年(1943年)から見ることのできなくなった猛獣サーカスも、昭和27年(1952年)のころから興業をはじめるようになった。しかし失明した私には、あの少年のころのように、動物たちを実際にみることはできなかった。
◇
昭和30年代に入ると、昭和24年(1949年)に市政をしいた秩父の夜祭りの内容は、すこしずつ派手になっていき、また賑やかさもましていった。
昭和44年(1969年)10月、西武線が開通し、秩父公園のそばに大きな西武秩父駅ができると、秩父夜祭りは観光ブームにのって、さらに盛大になっていった。
p126
何年かまえに、妻と息子2人の家族連れで秩父夜祭りを見物にいったときのことである。西武秩父駅で下車し、駅の前にでると、そこには小さな小屋が建てられ、その中で少年たちが秩父屋台囃を真剣にはやしているのをきいて、なんともいえない懐かしさをおぼえた。
はじめて秩父囃を真近かにきいた妻などは、まるで自分の里の囃を聞いているかのように、すばらしい、すばらしいといって興奮していた。私はこうしてよろこんでいる妻に手をとられながら、肉眼で充分に見ることのできた、かつての幼いころの秩父夜祭りの情景を、瞼の裏に妨佛とよみがえらせていた。
私は瞼のなかに、あの柴田サーカスで、虎と格闘をしていた24、5歳の若い娘の、白いセーターに紺色のズボン、胸には大きな赤い蝶ネクタイをしていた姿を、くっきりと思いうかべることができた。
また私が屋台囃をはじめたころ、私に囃を真剣に教えてくれた太鼓たたきの名人で、あんまを業としていた、加藤猪助、通称いのちゃんと、また同じあんまを業としていた笛吹きの名人、太幡助次、通称すけちゃんの姿も、思いうかべることができた。
p127
いのちゃんもすけちゃんも全盲で、稽古のときは非常にきびしくやかましかったが、それ以外のときはやさしく親切だった。すけちゃんは亡くなったと聞いているが、いのちゃんは健在で、秩父市内のどこかでひっそりと暮らしているということだ。
できることならば、久し振りにいのちゃんと逢って、少年のころの夜祭りの思い出を、じっくりと語り合ってみたいものである。
恐ろしい悪夢・伝染病の感染・・・p128
p128
昭和15年(1940年)の夏はとても暑かった。私は小学校の3年生になっていた。
その年は紀元二千六百年ということで、万世一系の天皇制の歴史を祝う式典が行なわれる年にあたっていた。日本国民は、神国日本が二千六百年もの長い歴史をもち、ずっと天皇制が培われてきたということに、大きな誇りをもっていた。
そのことで国中が狂気のごとく湧き返っていたのであった。
金鶏輝く日本の
栄えある光身にうけて
いまこそ祝へこの朝(あした)
紀元は二千六百年
あゝ一億の胸はなる
という、紀元二千六百年を祝う歌が国中でうたわれた。
p129
私もこの歌を誇りをもって声高らかに、友人たちといっしょにうたったものであった。
またその年は、日独伊三国軍事同盟が結ばれた年でもあり、あの太平洋戦争の勃発する前の年でもあった。
◇
その年はどういうわけであったかわからないが、秩父の夏祭りが例年のように、7月の19日と20日の両日ではなく、14、15の両日に繰り上っていた。
私は、14日の午前中にでき上った八棟の大きな屋根をもつ、本町の山車を友人といっしょに見にいった。山車のそばには、その年囃し手に選ばれた柴崎忠二のほか3人の少年が、紅白の衣裳を着け、拍子木の役に選ばれた10人ほどは、青赤の染め分けを、いずれも肩ぬぎにしてさもうれしげに山車の方を向き、何かしゃべりながら、たのしそうに立っていた。
私はそのとき、彼らがとてもうらやましく思えた。なぜなら私は、どんなに泣いてももがいても、囃し手にも拍子木の役にもしてもらうことはできなかったからである。
p130
山車をもっている町内の少年たちには、この囃し手か拍子木の役になるということは、誰にでも自慢できる一代の誇りであったから、どんな少年でもみなその役になりたがっていたのである。
正直をいうと、私もぜひその役になってみたかった。しかし私は視力障害があるので、その役にはどうしてもしてもらえなかったのである。このとき、視力の弱い自分をどんなにのろったことか、余りのくやしさ悲しさに、家の者のいないところで泣いていたのを、よくおぼえている。
私はそのくやしさを吹きとばしたいために、山車の曳き綱にずっと掴まりっきりであった。夢中で山車を引き、あちらこちらでくれる、アイスキャンデーや、アイスクリーム、氷あずきなどを、むやみやたらと食っていた。
昼間ひと通り山車を町中引きまわしたあと、止ったときに貰った赤飯も腹いっぱい食べた。私はその日はいつもとちがって、意地きたなくどんどんがむしゃらに食べた。夜も山車の曳き綱につかまって夢中で引っぱって歩いた。
p131
梅雨はまだ上っていたわけではなかったが、その日は天気だったので大ぜいの人が大通りを埋めつくし、町は非常な賑わいであった。山車の周囲や柱や屋根に飾りつけられたぼんぼりの、ひとつひとつに灯が点されたので、山車はひときわ美しくみえた。そのぼんぼりの灯が暗い夜空に映えて、夏の夜祭りの雰囲気を充分にかもしだしていた。
その名も高い屋台囃や、囃し手の声や、拍子木の音などが、綱を引くものにさらに元気を湧き立たせた。わっしょい、わっしょいという威勢のよい声が家並にこだましていた。山車を引き回している模様を、山車をもっていない町内の子どもが、しばらく山車についてじっと眺めていたが、とうとうがまんができなくなったのか、綱に?まって引こうとした。とそのとき、上級生たちが、
「おい、おまえはうちの町内ではないじゃないか、手をはなせ、はなさないとなぐるぞ」
といってその少年の手を綱から引き離した。少年は悲しそうな顔をして、綱から離れていった。
p132
私はその少年にも山車の綱を引かせてやりたかった。しかしまだ小さかった私には、上級生のおそろしい顔が気になって、
「おい君もここへきて、いっしょにひこう」
といってやることができなかった。
そのときの模様をいま思いうかべるとき、私の息子が4、5歳のころ、私の母の作ってくれたきれいな祭り袢纏を着て、よろこび勇んで他の町内の山車を引きにいったとき、その町内の子どもから、
「おまえはこの山車を引いてはいけない」
といわれて追い帰され、泣いて帰ってきたのを、ふと思い出したのである。
だからあのとき、綱から引き離された少年がどんなにくやしく悲しい思いで家に帰ったかを、想像することができた。
私はその夜、力のつづく限り綱を一所懸命引いたので、その夜の全行程が終ったときは、ぐったりしてしまった。なにか異常なけだるさが私をおそった。そしてまた、体もなんとなく熱っぽかった。この異常なけだるさと、妙なあたたかさは、翌15日の朝になっても私の体から消えなかった。
p133
昨日、一所懸命、山車の曳き綱を引いたので、その疲れがまだ残っているのではないかと思い、私はあまり気にもしなかった、
その日の午後になると例年のように、御川瀬(おかわせ)といって、秩父の神々が川を浄めなさる行事があるのだが、山車はその神々を追って、中村町というところまで引き出され、そこで川を浄めて上ってこられる神々を迎え、また神々のあとにしたがって、各町内へもどるということになっているのだった。
12月の冬の夜祭りよりはいくぶん小造りの山車が6台そろって神社に集るので、その日の神社の境内はとても賑わい、またその7月の祭りは子どもの祭り、といわれていることもあって、境内は子どもの声でいっぱいであった。
◇
この日も例年どおり山車が、秩父神社から道生町(どうじょうまち)を通り中村町を下っていった。私は一所懸命曳き綱をつかんでいたが、とうとう体が熱くだるくて、そうしていられなくなり、残念ながら父といっしょに家に帰ったのだった。
p134
家に帰り母に体温を計ってもらったら、驚いたことには40度もあった。間もなくして不気味な水溶性の下痢がはじまり、それは10分の間隔もまたず、ずっと続いていった。便の色がどんな色をしていたか、よく記憶していないが、間もなく私はぐったりとなって、意識を失ってしまったのである。
その日の午後から夕方にかけて私は時おり、意識をとり戻したり、また朦朧となったりしていたようである。熱の方はいぜんとして40度を下ることはなかった。母の、おろおろする声がきこえたような気もしたが、もう下痢は5分おきくらいになり、私はだんだん衰弱し体力を消耗していったのである。
母は築田多吉著の『実際的看護の秘訣』通称赤本と呼ばれている家庭医学書をよみ、私にどろどろとした蓖麻子油をのませ、それから一時間たったころ、梅肉エキスを口のなかに流しこんでくれた。
また二時間たってから蓖麻子油、さらに一時間たって梅肉エキスという方法で、何回もこれをくり返し私の口のなかに入れた。私はこの母の強烈な療法をうけながら、朦朧とした意識のもとで時を過していた。
p135
その夜の8時ごろ医者がきて、強心剤のようなものを打ったようであったが、私は注射をしてもらった感覚を、まったくしらなかった。翌日になっても母はまだ、蓖麻子油と梅肉エキスの療法をつづけた。
朝だというのに、体温はすでに40度をこえていた。午前9時ごろになって医者がやってきたが、医者は私の体を診察しながら、母にむかって、
「重体だ、危い、避病院に入院させなさい、急がなければだめだ」
と沈痛な声でいっていた。私はこのとき、偶然にもその医者の声をきくことができた。医者の診察が終ると、私はまた意識を失った。
あとから聞いた母の話によると、そのときの私の心搏動はときどき停止し、呼吸のみがつづき、また心搏動が再開始し、呼吸は大きくふかく、それからだんだん浅くなる、という状態を何度もくり返していたという。
意識が回復したとき、私は何人かの人に担がれて、家の裏口から出て、周囲を黒い布で覆われた不気味な二輪車にのせられた。それは伝染病患者がのせられる死の黒車、と人は呼んでいたが、まさか自分が乗せられるとは思いもしなかった。
p136
黒車の中でも、意識を失ったり戻したりをくり返していた。
意識が回復したのは、強心剤の注射を打ったときのようであったが、このときも注射をされたような感覚はまったくなかった。それにまた、何回も下痢をしていたということであるが、その感覚もまったくなかった。
私は朦朧とした意識の中で、避病院に連れていかれるのかなあ、と思ったりしたが、この黒車が避病院に行くのだ、ということは、私に誰も知らせてはくれなかった。
避病院に着いたころ、私はまた意識を失ってしまった。意識が戻ったときは病室の中だった。その病室には8台のベッドがあり、そこに私と同じような子どもの患者が寝かされていたことを、おぼろげながら見ることができた。私はそこで間もなくまた意識を失った。
◇
その後、意識を回復したようだったが、そこは避病院のなかではなく、なんとも不気味な暗い洞窟の中のようなところであった。
p137
ふと気がつくと、すこしはなれたところに、鉄格子のはまった出口のようなものがあり、その向こうから明るい日の光がさしこんでいた。
私はその出口にかけ寄って鉄格子をあけようとした。しかしいかに工夫しても、どうしても、その鉄格子はビクともしなかった。格子の向こうからは、明るい若者の声や、年寄りの声、きれいな女の声、かわいらしい子どもの声などがきこえてきた。
私はおどろいて鉄格子に顔をすり寄せて外をみると、そこには美しい花々の咲き乱れた楽園がいっぱいにひろがっていた。それらの声の主は、そこで喜々として遊びたわむれていた。私は必死になってその人たちを呼んだが、私の口からは声はでなかった。
楽園の中で遊びたわむれている人たちは、鉄格子の中にいる私に気がついたのか、さかんに手招きをして、
「こちらへ来なさい、早くこちらへ来なさい」
と呼びかけてくれた。私はいっそうあせって全身の力をふるい、鉄格子を動かそうとした。
p138
しかし鉄の格子戸は、やはりびくともしなかった。私はそのうちに、しだいに体力を消耗していくのをおぼえた。そしてやがて意識を失ってしまったのだった。
どこかで聞いたような声が朦朧とした私の耳にきこえてきたので、目を開けてみると、霧の中に母や父や姉、叔母などの顔が、代るがわる私をのぞいていた。
私は必死に両手を動かして霧の中でもがいた。そして精いっぱいの声で、父母や姉や叔母を呼んでみたが、その声は私自身にはすこしもきこえず、私は疲れて眠りに落ちていったようである。
◇
昼だか夜だかよくわからなかったが、かなり長い時間ねむりつづけていたような気がした。その後もおぼろげながら、避病院に入院しているということだけは知っていた。ときどき、何か太い注射のようなものをされた感触をおぼえたが、それは別に痛くも苦しくもなかった。
p139
母があとで話してくれたが、そのころの私は生死の境をさまよっているときらしく、霧の中でみた父母や姉たちの顔は、事実、ほんものの顔で、危篤状態の私を見舞いにきたときの顔であったそうだ。
するとあの鉄格子のある洞窟の意識は、恐らく夢だったにちがいない。そのときの私の魂は、危うく天国に招かれていくところだったのであろう。
あの鉄格子から見た向こうのすばらしい楽園は、天国だったにちがいない。もし私があの鉄の格子戸を開けて、楽園に足を踏み入れれば、そのまま私は天国に召されてしまっていたかも知れない。
思い起してみると、その夢はじつに、えもいわれぬ美しい情景であった。
◇
体温と脈の変化を表示した図表を、ずっとあとで見せてもらったとき、生死をさまよっているときの曲線が、するどく上下しているのをみて、病気がどんなに恐ろしいものであったか、ということを、改めて知らされたのである。強心剤1本しか人の生命を守る方法がなかった時代にあって、生きのびたということは、まさに天運に恵まれたというほかはない。
p140
病状のもっともはげしいときは、無意識状態であったので、胸苦しさも腹痛も、その他のいろいろな症状も、全く感覚に残らなかったということは、不幸中の幸いというほかはない。
避病院に入院して3日目、発病以来4日目の夕方になって、はじめて緑便のなかに普通便のような色が混ってきた。意識もそのころからはっきりとよみがえり、母もようやく私が死期を脱したことを知り、ほっとしたようであった。
三度の食事はおもゆとスープだった。おもゆはどうにか飲めたが、スープはなかなか飲めなかった。スープが飲めるようになったのは、何日かしてからのことである。私はそれでも、一命をとりとめたことを大いによろこび、おもゆやスープを一所懸命のんだ。そして完全に治癒する日のくるのを、1日も早くと待っていたのである。
1週間目からおまじりになり、起き上ってスプーンをつかって食べた。おまじりはおもゆの中に、わずかのめし粒が混っているだけのものであったが、私はそれをスプーンで食べるのがとてもうれしかった。
p141
それから一日一日と日が経つにつれて、すこしずつめし粒の量が多くなり、二分がゆ、三分がゆ、五分がゆ、七分がゆとなり、やがて全がゆにうつっていった。
便の検査は1週間目に1回目の検査があり、それに合格すると、それからまた1週間目に、2回目の検査があった。2回目に合格すると、それ以後の状態に変化がなければ、近日中に退院してもよい、という許可がでた。
私を見舞にくる者は、病棟の入口の所で消毒液で手足を消毒し、また帰るときも同じ場所で、3種類か4種類のクスリで厳重に消毒して、帰ったようである。
私に付添い、いろいろ世話をしてくれた看護婦は、黒沢という若い独身の、とても親切でやさしい人であった。
私が入院していた18日間に、この病院では10数名の患者が死亡した。午後5時ごろ入院して、その日の8時ごろもう息を引きとる人もいた。あとで知ったことであるが、私と同じ病室にベッドを並べていた、他の7人の子どもの患者は、みな亡くなってしまったということであった。
その話をきいたとき、私はぞっとして、何ともいえない冷たい汗が背すじを流れるのをおぼえた。
p142
退院の日、手足を消毒したのち、別棟の病棟に連れていかれた私は、そこで薬湯の風呂に入れられ、全身を洗われて、まあたらしい着物を着せられ、18日振りに家に帰ることになったのである。
迎えにくるタクシーを待っている間にも私は、不気味な二輪車の黒車が、避病院の門をくぐってくるのをみたときはっとして、重苦しい気持ちにさせられた。
だけど私は、その車から目をそらすことはできなかった。
見るとその車から、手足のやせ細った顔色の悪い、今にも死にそうな子どもの患者が運び出され、病棟へつれ去られるところであった。私はそのとき、18日前の自分の姿をそこに思い浮かべ、思わず「あゝ」と嘆息をもらしてしまったのである。そして心の中で、その患者が丈夫になって一日も早く退院できる日のくるのを、祈ったものであった。
私は迎えにきたタクシーの窓から、真夏のギラギラした太陽の輝く明るい秩父の町を眺め、道みちの緑の木々をみて、生きていることのよろこびをしみじみと味わったものであった。
p143
◇
入院中は、何を食べてもうまくて、全く好き嫌いというものはなくなったように思われた。家に帰って食事をするとき、家族のものは私に気をつかって、まだ私の食べられないものが出ると、まずい、まずい、といいながら、芝居っ気たっぷりに、いかにもまずそうな顔をして食べていた。
母の話によると、私の病気は、赤痢であった。母は『実際的看護の秘訣』という本の中での、梅肉エキスと蓖麻子油の交代療法で成功したと思っていたから、著者の築田博士に、そのことを手紙に書いて送ったようであった。
すると間もなく築田博士から返信があって、博士の手紙には、母を讃え、母の手当がよかったから私の命が助かったのだ、ということが書かれてあったとかで、母は大へんよろこんでいた。そしてさらに博士は、その中に、梅肉エキスを常備薬として私にのませるように、勧めていたという。私はその夏中、梅肉エキスを毎日1回のまされていたことを、おぼえている。
p144
私の家は、私が赤痢に感染したということで、家中、隈なく消毒され、5日間ほど営業停止になった。家族のものや、使用人のすべてが便の検査を強制的にさせられたようだ。私はそんなことで、家のものに大へんな迷惑をかけてしまった。しかし母は、そのことは私にひと言もいわなかった。
赤痢から開放されたとはいうものの、私の体力はすぐにはもどらなかった。だからしばらくの間は、男子の友人たちと同じように戦争ごっこやちゃんばら、山登りなどをして遊ぶことができなかった。
したがって遊び相手もしばらくの間、女子に求めざるを得なかった。そのころの女子はなかなかいさましく、ひ弱になった男子の私などから見れば、はるかにたくましいものがあって、私はときどきその女の子たちに組み伏せられたりして、泣かされそうになったこともあった。そんなとき、女の子たちは私にむかっていつも、
「そんな弱虫では、とても立派な兵隊さんにはなれないわね」
といって、私をみつめていた。
p145
私はそういうことをいわれると、ほんとうに立派な兵隊さんになれないかも知れない、と思いなやみ、苦しんだものであった。
◇
昭和33年(1958年)の夏に、私はもう一度、赤痢に感染した。しかしそのころは、すでに抗生物質のストマイ療法ができていたので、私はその恩恵に浴して、それほどひどい目にあわず、あの恐ろしい避病院にも入院せず全快してしまった。
また、私の赤痢がかるかったということで、当時のように家中のものに検便やら、消毒やらという迷惑をかけずにすんだことは幸いであった。
だがどういうわけか私は、ストマイアレルギーをもち合わせていたようで、ストマイの注射を打つと、顔面神経麻痒になり、右側の耳ががんがんと鳴る副作用に苦しまねばならなかった。
そんなときに私は、あの自然薬である梅肉エキスや蓖麻子油の効果の、じつに偉大なることを、改めて、しみじみと思い知らされたものである。
縁故疎開の児童たち・・・p146
p146
昭和18年(1943年)の秋をむかえた私は、小学校の6年生、12歳になっていた。
2年ばかり前にうけた開眼手術の成功で、学習もどうにか授業の内容についていけるくらいの力になっていた。
そんなとき日本は、太平洋戦争の泥沼に入りこみ、敗戦への途をたどっていた。
ラジオからは軍艦マーチの景気のよい音楽に合わせて、大本営発表の、勝利の大戦果を報道していたが、不思議にもそのよろこびは、なぜか空虚な響きをもって銃後の国民に伝わっていたのであった。
私のような小学生でも、勝利、勝利とはやる心でいながら、一方では生活の統制がしだいにきびしくなり、生活物資が充分に手に入らなくなってくるのが、どう考えても不思議でならなかった。
p147
それから間もなく大都会は、敵米軍機によって空襲されるであろう、ということがうわさされるようになり、やがて縁故疎開とか、集団疎開というようなことが、ささやかれるようになってきたのだった。
昭和19年(1944年)になると、大都会から遠くはなれた田舎町などに、親類縁者のあるものは、家族ぐるみでそこをたよって、縁故疎開をした。父親の仕事上の都合で、家族がいっしょに縁故疎開ができなければ、その子どもたちだけでもということで、親類縁者にあずけられる者もいたのである。
◇
昭和19年(1944年)の4月、新学期をむかえると、そうしたケースで田舎町に疎開をしてきた東京の少年少女が、私たちの町にもぐんとふえてきた。疎開をしてきた東京の少年少女の転校は、土くさいこの田舎の小学校に、あたらしい都会的なふんいきを、吹きこんでくれた。
p148
この少年少女たちは、都会の水で品よく育ったせいか、顔の色が白く、その大部分のものが男子は凛々しく理知的な顔をしており、女子はうつくしく愛らしい顔をしていた。だから色の黒い団子っ鼻の田舎むすこや田舎むすめの中では、ひと目でそれとすぐわかった。
そうした疎開の児童の中には、世が世ならば私などがとうていそばにも寄れないような、華族さまの御曹子や令嬢などもいた。だが彼らはそんな身分のことなどは忘れたように、田園地帯の豊かな太陽のひかりと、新鮮な空気のなかで、私たちと仲よく思い切りかけまわったり、学習に励んだりしていたのである。
私たちもこの新しい疎開の友だちを、よくありがちな他者(よそもの)あつかいにはせずに、地元の栗原徳太郎や、山中康道らと、いつもいっしょにお互いに日本の少年少女たちなんだ、ということで仲よくつき合っていた。
田舎の小学生は、疎開してきた都会の小学生からいろいろな新しい知識をふんだんにさずけられた。そのかわりに私たちも、疎開をしてきた都会の小学生に対し、田舎でなければとうてい味わえない、いろいろな面白い健康的な遊びを教えたりした。
p149
昭和20年(1945年)になると、秩父の町にも集団疎開の児童が入ってきたのであるが、私は彼らとほんの5、6回しか語り合う機会がなかったので、縁故疎開の児童たちとの記憶の方が、鮮やかに残っている。
◇
いちばんはじめに友だちになったのは、須山薫夫、恒行の兄弟と、石橋正光という三人の少年たちだった。彼ら三人の少年は、私の住んでいる本町にある、麻屋という屋号の酒店に移ってきたのだった。
その家は3人の母親の生家だということで、3人はきわめて気軽にその家で生活していた。薫夫は3年生にしては背も高く、体ががっちりしていて、弟思いのやさしい性格をもっていた。弟の方の恒行も、兄のいうことをよくきき、2年生ながら辛棒強く田舎の生活に耐えていた。
石橋正光は4年生で、温厚な少年であった。その顔がまん丸なので、お天道さまという綽名があった。須山兄弟はなかなかの美少年で、やさしい顔立ちをしていた。
p150
正光は読書が好きで、ひまさえあればよく本を読んでいた。だから知識の面では彼がいちばんだった。彼は物語が得意で、話し方がなかなか名調子であったから、私も好んで彼の物語をよくきいたものである。
当時の私は防空頭布を肩にかけ、松葉杖をつき、眼鏡をかけていたので余りいい格好ではなかった。とてもガキ大将になれるような柄でもなかったが、須山たち三人は、田舎の子どもたちといっしょに、よく私のいうことを聞いてくれて、仲よくたのしい毎日を送っていた。
須山たちの住んでいる麻屋の店の前に、間口も奥ゆきも大きな2階建の、がっしりした銘仙問屋があった。そのころは戦局も激しく悪化してきたので、そんな所で銘仙を派手に売るようなことは、できなくなっていた。
だからその大きな建物は空家同然になっていたので、とくに住む家もない縁故疎開の人たちは、その空家の大きな建物の中に、何組か自然に住みつくようになっていた。
土谷真司の家族もそこに住んでいる一組であった。土谷真司は須山薫夫と同学年であるが、須山兄弟とおなじく顔立ちがよかったので、白襟の慶応型の洋服がよく似合っていた。
p151
真司の家族は両親と姉と、弟の五人家族であった。
真司の姉の高子は背がすらりとのびて、小学校の六年生だったから、髪はオカッパにしていたものの胸はやや丸みをおびて、なんとなくむすめらしく、顔立ちもとても愛らしい少女だった。私はなんども絵に描きたいような衝動にかられたものである。
そのころ高子は、町内の男子生徒のあこがれの的になっていた。当時、評判だった、隣りの町内のたばこ屋のむすめよりも、高子の方がはるかにきれいということで、人びとのうわさにのぼっていた。
高子は翌年、高等女学校に入り、女学校の制服を着て表を通るようになったが、その制服を着た高子のうつくしさが格別だったので、男子の間では、またも高子の話でもちきりであった。
◇
田中信義は私とはじめて会ったときは、小学校の2年生であった。信義は体は小さかったが、非常にがまん強い少年で、勉強もよくできた。
p152
女の子のようなやさしい顔立ちをしていて、いつも姉の赤い足袋をはいていたので、私たちは信義のことを赤たび、赤たびと呼んでいた。
この信義は、私が失明してからのち、3、4年もの間、私に100冊以上もの本を読んでくれた、大へんな奉仕者だった。彼は手先はそれほど器用ではなかったが、とにかくねばり強い性格で、そのことを最後までやってくれた。
信義には二人の姉と、妹と弟がいた。二人の姉はともに頭脳が優秀で、とくに長女の久子は私より年上であったが、すらりと背が高く、彫りの深いなかなか理知的な顔をしていた。次女の文子は私より一つ年下だったが、やや丸めの明るい顔立ちで、土谷真司の姉の高子と同じように、小学校の6年生なのに、胸がふっくらとして、むすめらしい美少女だった。
信義の家族は、父親が東京に残り、母親と五人きょうだいで疎開していたのだったが、みな仲よくお互いに励まし合って頑張っていた。長女の久子はその後小学校の先生になって、一所懸命教育にいそしんでいたが、私が失明して間もなく、太腿四頭筋肉腫、という恐ろしいガンにかかり、19歳の若さで天国へ召されてしまった。
p153
◇
田中信義と同学年に、高橋昭という少年がいた。昭は銘仙販売所の大きな建物の中に、両親と3人で住んでいた。顔の細長い色の白いひ弱な少年であった。
私は昭の両親に「この子を丈夫な子どもにしてちょうだい」とたのまれたので、いい気になって、昭をよくしごいたものだ。
昭は最初はしごかれるとめそめそしていたが、しだいに頑張り少年にかわっていき、3年生になったころには、ついに、空中転回や、とんぼ返りも平気でできるようになった。
そうなったころには、体もかなりしっかりしてきて、顔も黒く日にやけ、色つやもよくなってきたが、気持ちの方はもうひと押しというところで、どこかに、まだ気弱なところがみられた。
昭和20年(1945年)になると、この3人の家族の中に井村三代子という昭よりも一つ年下の少女が加わった。
p154
この少女はなかなか勝気で、昭と体格もそうかわらず体もふとって、がっちりしていた。三代子という少女は、昭の両親がいないとからかって、昭にとびつき畳の上に組み伏せたりした。
三代子は勝気なところはあったが、まつ毛の長いかわいらしい顔立ちで、多くの人からかわいがられた。私もよく三代子をからかった。からかったときに私が負けた振りをすると、三代子は平気で私の胸の上に馬のりになり、「弱いお兄さんね」といってよろこんだりしていた。三代子も色が白かったので、濃い水色系統のワンピースや、モンペの上下を着ると、ひときわ愛らしくみえた。
◇
本町の町内にある阿佐美薬局に疎開していた島田喜美子、武雄の姉弟もまた、仲のよいきょうだいだった。この二人の姉と弟は、心に悲しみが潜んでいたのか、一所懸命はしゃいだり遊んだり、とび回ったりしているときでも、顔のどこかに憂いがみえた。
それに小学校1年生の武雄は、よほど淋しかったのであろう、3年生になる姉の喜美子の胸に顔をうずめて、何かあまえていることがあった。
p155
喜美子は非常に足が早く、短距離の選手で、小学校の運動会ではいつも、町内対抗で本町チームのリレーの選手だった。
須山薫夫もとても足の早い少年で、やはり本町チームのリレーの選手だった。
この須山薫夫と島田喜美子の二人は、好1対の名選手であった。
島田武雄は姉の喜美子とちがって、足は決して早くはなかったが、そのかわり力が非常に強く、相撲も強かった。小学校1年生の割にはいい体格をしていた。
腹はいつも前に突き出ていて、吊りズボンを穿いていたが、そのうえ、腹の下の方にバンドもしめていた。
福田章二も、私の家の近くにある稲葉という豪邸に、家族で縁故疎開してきていた。やさしい顔立の少年で頭脳も優秀だった。福田はいとこといっしょに、私の家によく本を借りにきたり、遊びにきたりもした。この少年はのちの芥川賞作家の庄司薫である。
また、まつ毛の長い眼の大きい女子で、家にもときどき遊びにきたことがあるもこちゃんという子は、戦後SKDから映画女優となった野添ひとみである。
p156
しかしそのころには失明していた私は、残念ながらこの人の映画をみていない。
◇
私はそうした疎開児童らといっしょに、春は武甲山の麓の丸山に、秋は23番札所のある尾田巻丘陵に、よく遊びに行った。また夏の暑い日には、荒川の水音にさそわれ、広い川原におりて、水遊びにうち興じたりもした。
学校から強制されていた軍馬のための草刈にも、非常食に必要などんぐり拾いも、彼らといっしょに仲よくたのしく出かけていった。雄大なる武甲山をはじめ、秩父盆地の大自然は、私たちをそのふところで温かく育んでくれた。
彼らはその自然の中で、大きな声をはりあげて歌をうたい、キャッ、キャッとはしゃぎまわったりした。しかしそうした彼らも、その心のうちにはさびしい一面をもっていたようであった。その淋しさ悲しさは、私などには想像もできないものであった。
彼らは夜になると床の中で、東京にいる両親のことや、住み馴れた自分の家のことを思いうかべながら、恋しさ悲しさに耐えられなくなって、涙していたのだと思う。
p157
もし戦争さえなかったら、家族はお互い一つ屋根の下で一家団らん、たのしい毎日を送ることができたであろうに、家族ばらばらのみじめな生活にならなくともすんだであろうに…と思ったら、小さな私の胸も痛むのだった。
そうした惨酷な仕打ちを、国民は問答無用で強いられたのであるが、疎開児童たちはその痛みを、ひしひしと感じたことであろう。
武甲おろしが秩父盆地をすさまじく吹きまくると、秩父の冬はぐっと寒気がきびしくなってくる。しかし疎開の子どもたちは元気で、私たちといっしょに戸外にとび出し、陣とりや戦争ごっこ、縄とび、マラソンなどをした。正月には、しょうゆ焼きの僅かな餅をかじりながら、凧揚げ、羽根つき、竹馬乗り、独楽まわしなどに興じた。
またそのころは、非常にはやっていた模型グライダーや、模型飛行機の工作に夢中になったりしていたのである。
p158
もっとも寒気のきびしい冬の夜などは、炬燵の中で私たちといっしょに、乾燥いもをかじりながら、カルタやトランプ、兵隊将棋や双六などをして、気をまぎらわせていた。
縁故疎開の少年少女たちでさえ、このようにさびしかったのだから、まして集団疎開で、親元をはなれて遠く田舎町にきていた少年少女たちは、どんなにか淋しく、つらかったことであろう。
◇
こうしていろいろ思い出していると、かわいらしい小学生の彼らのひとりひとりの顔が、私の瞼の裏になつかしくよみ返ってくる。この児童たちもいまはそれぞれ立派な子の親となり、終戦日が近づくと、お互いに、わが子へあのころの苦労を語り伝えていることであろう。
私も、こうして疎開児童たちと接した尊い体験を息子たちに語り、二度と戦争をくり返さないことを、執拗に伝えていきたいものである。
秩父の町の進駐軍・・・p159
p159
昭和16年(1941年)12月8日に、ハワイ真珠湾の奇襲攻撃で、はなばなしく幕を開けた太平洋戦争は、丸4年8ヵ月にわたるすさまじい戦いののち、昭和20年
(1945年)の8月15日に、敗戦というみじめな結果で終末をむかえた。
絶大なる物量が、大和魂に鉄槌を加えたのであった。9月2日ミズリー号の甲板上で調印が終ったときから、アメリカ軍の上陸が開始されたのである。
◇
それから約2週間ほどたったころ、私の郷里の秩父の町にも、他の都会や町と同様に、100人ほどの米軍が進駐してきたのであった。町の大通りを10台以上のジープと、数台のトラックに乗り、緊張した米兵の顔が、銃を手にしたまま通りを見まわしていたのを、私ははっきりと記憶している。
p160
道路の端に立ってそれを見ていた人びとの顔もみな緊張し、口ぐちに「アメ公がきた」「毛唐がきた」とささやいていた。 「女どもは家の奥へかくれろ」という者もいた。
ついひと月ほど前までは、鬼畜米英め、ヤンキーめ、といっていた神国日本の国民だったのだから、警戒するのは当然のことであろう。とにかくそのときは、大勢の人びとが道路の脇に立って、このジープとトラックを、おそるおそる眺めていたのであった。
ちょうどそのころ、6人乗りのジープが、この町で旅館を営んでいた私の家の前に、ぴたりと止った。私の父は、米軍と県の要請で、秩父町の旅館組合の指示をうけて、6人の米兵を投宿させることを了解していたのであった。
ジープの前には米国陸軍写真班と筆太の日本文字で書いた標識をつけていた。
そして車の中から6人の米兵が降りてきて、私の家の前に整列した。見るとその男たちは、4人は6尺豊かな大男であり、あとの二人は、日本人と余り背丈の変らない小柄な男だった。
p161
4人の大男は赤いひげ、青い目の典型的な西洋人の顔であったが、二人の小柄な男は、黒い髪と黒い目の、一見、日本人のような顔つきをしていた。
一同は駆けつけてきた通訳から注意をうけ、きちんと靴を脱いで部屋に入った。
夜、玄関の上りがまちのところで、米兵のキャプテンと父は、通訳の介添で、投宿に関する諸種の契約をとり交わした。通訳の英語がきわめて流暢だったので、話はとんとんと進んだ。
家の玄関前には、何十人もの群集が家の中をのぞきこんで、珍らしそうに、また興味ありげなまなざしで、この光景をながめていた。
◇
6人の米兵は、最初の3日間は、家の中のどこへいくにも決して剣銃を腰からはなさなかった。洗面やトイレにいくときも、すこしも油断をみせなかった。私の家の中での米兵の行動は、いつもきちんと決まりを守っていた。通訳が一日に1回の連絡にやってくる以外は、兄の英語でどうにか間に合っていた。
p162
家の使用人のうち、彼ら米兵がメードと呼んでいる女中たちは、日米英語会話手帖という簡単な手引書を買いこんで、それで会話を練習していた。発音もまったくでたらめな即興の会話であったが、女中たちの不思議な英語は、どうにか米兵に通じていたようで、適当に用はすまされていた。
米兵たちも、小柄な日本女性がカタコトで話す英語に、とても興味をもったらしく、辛棒強くそれを聞いてやっていた。
5日ほど経つと、幾分安心したのか、腰から剣銃をはずし、1週間ほどたつと軍服を脱ぎ、気軽な服装になって、家の中を歩きまわるようになった。そして玄関のそばの囲炉裏端にやってきて、日本茶をのんだり、父や兄といっしょに日本酒をのんだりして、くつろぐようになった。また翌年に亡くなった姉の淑子は、まだ元気で秩父高女の教師をしていたが、この姉の弾くピアノの伴奏で、フォスターの名曲集を歌ったり、クリスマスソングを歌ったりもしていた。
人前ではめったに歌ったことのない姉の淑子が、ソプラノでフォスターの名曲集を、ピアノを弾きながら歌っていたことが、今も忘れられない。
p163
10日ほどたつと米兵たちは、宿の浴衣を着たり、またワイシャツ姿で表に出たりして、気軽に過ごすようになった。6人の米兵は、みな派手な柄の日本の着物をみやげものとして買いこみ、それをトランクの中に詰めてよろこんでいた。
◇
米国陸軍写真班、という中央からの命令できた彼らは、みな紳士ぞろいだった。
キャプテンのランダン・モーリスという男は大尉で、30歳くらいの落着いた風貌をもった男だった。全員の名前はおぼえていないが、20歳そこそこのチャプマンという、かわいらしい少年のような兵士と、ジェームスという映画俳優のような美男子の顔は、なんとなく記憶に残っている。女中たちの中でも、この3人の外人の印象は強かったらしく、彼らが帰国したのちでも、時おりうわさ話などをし合っていた。
ダンスをするということは、男女が抱き合って踊るということで、不道徳のように思われていたが、彼らに手ほどきをうけ、一度たのしい気分を知ると、女中たちもポータブル蓄音機をかけて、さかんにダンスをたのしむようになった。
p164
女中のなかでも、恵美子や春子は特に積極的だったので、ジェームスやチャプマンにも大変よろこばれた。
米国陸軍写真班の6人の兵士は、予定された投宿の日がおわるころになると、すっかり私の家の者と親しくなり、帰る前の夜、囲炉裏端に家中全員を集めて、写真をとってくれた。また要求に応じて、個人の写真もとってくれた。
そして何百枚もうつした写真を、何冊ものアルバムにきちんと整理しておさめ、英語で何かしきりに書きこんでいたようであったが、それがすっかりおわると、私たちにそのアルバムを見せてくれた。
写真の内容はほとんどが日本人の生活の実体を写したものであった。そこにはたすき掛けで、釣瓶井戸から水を汲んでいる長屋のおかみさんの姿や、どろ遊びをしている、かわいらしい子どもたちや、農耕にいそしんでいる農夫の姿などが、白黒のくっきりした写真となっておさめられていた。
◇
米国陸軍写真班が去ったあと、私の家はGHQの指定旅館となったので、土曜から日曜にかけて、米兵の将校やその家族あるいは、若い女をつれた米兵などが泊るようになった。
p165
米兵のよくいう、キスということばの意味は分るようになったが、パンパンということばの意味は、全く分らなかった。私の家に泊る米兵が連れてくる、若い日本の娘のことをパンパンガールと呼んでいたから、そのうちにそれが、男女の肉体関係にかかわることだということだけは、なんとなく分ってきた。
私は米国陸軍写真班の、きわめて紳士的な6人の兵士と最初に対面した印象が強かったので、このような日本の娘を連れてくる米兵の顔つきが、なんとなくいやな感じでならなかった。
秩父の町に駐屯した100人ほどの兵士たちは、幸いなことにその大部分が、おとなしい兵士たちであった。それでも彼らが銃を肩に町中をのっそりのっそり歩く姿は、やはりいい気持ちのものではなかった。なぜかといえば、いつ何どきその銃口が、こちらを向いて発砲されるか分らなかったからである。
p166
戦時中でも、刺青を二の腕に彫って、肩で風を切って町を歩いていたずんどこ兄いも、ちょっと気をそがれる感じで、米軍が駐屯してからは、しばらくおとなしくしていたことでも、町の雰囲気が一変したと感じられた。
そんなわけで、秩父の町中は、100人の駐屯兵のほかに、レジャーでやってくる米兵と、若い日本娘の数が多くなり、どこかに異国風のムードがかもし出されていったのであった。
私が生まれてはじめてヌード写真をみたのは、このころである。そのヌード写真は首から上と、膝から下が写っていない、まことに気味の悪い不思議な写真であった。しかし思春期をむかえたばかりの私の心に、その奇妙な写真は、きわめて強烈な印象を刻みこんだことは確かであった。
◇
年が明け、昭和21年(1946年)のあたたかな春がやってくると、自由主義とか、アプレゲールとかいうことばが巷に氾濫し、きわめてつつましやかであった大和なでしこが、服装も派手になり、あっという間に大胆な戦後派娘に変身していったのである。
p167
私はそうしたころ、駐屯兵と日本娘が、ちょっとした暗がりなどで抱きあっているのをよく見かけ、驚かされることがあった。ある日、私の友人の姉のそんなすがたを見たとき、私は唖然として、それっきり友人の姉の顔を、まともに見ることができなくなってしまったこともある。
私の家に泊りこむ米兵と女のなかには、無軌道な者がいて、他の泊り客のことなどまったく無視して、深夜に入浴したり、連れてきた日本娘を、大声あげてののしったりする者もいた。
そうしたある日のこと、余りそれがひどかったので、父はGHQに願いでて、その規制を要請した。するとGHQは、MPを各地に派遣し、女を連れて日本旅館へ泊ってはいけないこと、みだりに場所をわきまえず、みだらな行為を行なってはならないことなどを、徹底指導したためか、それからはしばらくの間、しずかにおとなしく泊るものが多くなった。
いままで若い日本娘をつれて泊りにきていた米兵は、それからは遊郭へ足をむけるようになった。だが米兵の中にも、GHQの指導とは関係なく、真の意味でのレジャーと観光を目的にして、この町を訪れ私の家に宿泊する者もいた。
p168
◇
私の家にかならずひと月に1回泊りにくる、ラッセルという中年の米兵も、そうした真の意味での、レジャーと観光をたのしむ一人、といってよいであろう。
ラッセルは40歳すこし過ぎたくらいの古参兵だったが、とても紳士で、私の家の者とも親しくなり、2番目の姉の喜子の英語のよき先生でもあった。
ラッセルは、アメリカに妻と二人の子どもを残しているということで、とても家庭的な雰囲気を強く慕う米兵であった。ラッセルはほんのわずかしか話せない日本語をつかって、私にもさかんに話かけ、気をつかってくれた。
また、近所の店にくる日本人ぐらいの背格好の、デニーという米兵は、童顔の明るい、人なつこい性格で、チョコレートをくれたり、おもしろい遊びをしてくれたりして、町の少年少女たちにとても慕われていた。
半年ほどの間には、町の人と駐屯兵との間に多少のトラブルはないではなかったが、それが波及して大きな事件に発展するようなことはなかったし、また暴力沙汰で、町の人たちが大きな迷惑を被ることもなかった。
p169
だから人びとは、進駐軍に対しての警戒の目を、しだいにやわらげるようになっていった。
このように秩父の町では、米兵の多くは住人に対し真摯な態度で接していたようだが、他の地に進駐した米兵のなかには、窃盗、掠奪、婦女暴行、殺傷などの事件をひきおこし、住民の生活をおびやかしていたという話をきいている。私はそうしたことを、単なるうわさでなく、日本が独立国となったあと、公に新聞やラジオなどで報道されたとき、あらためて戦争が人間を狂気にさせる恐ろしさを知らされた。
◇
もと水夫長をしていたという私の友人の父は、物のよく分った、世界を股にかけて航海していた人で、ときどき私の家に遊びにくると、
「日本の兵隊が支那でしてきたことの悪さは、彼らアメ公の比ではないよ。彼らは我々がはむかわなければ、その大部分はいちおう何も悪いことはしねえからね。
ところが日本兵の多くは、支那人が何もしないのに乱暴し、女を犯し、物品を掠奪したではないか。
p170
もし彼らが何かをやったとしたって、正直いってまったくのおあいこで、文句をいえた義理ではないよ」
「ところが彼らはみな紳士じゃないか。南京の大虐殺の真相を支那人からきいたことのある俺からいわせれば、まったく信じられないような平和な町の風景じゃないか」
「戦争なんぞというものは、一部の軍閥や財閥、狂信者の奴らがよろこんでいるだけで、俺ら一般の国民は決してうれしいものじゃない。みんな気が狂ったようにおかしくなり、人殺しや掠奪を平気でやってのけ、それが偉いということになるんだからなあ」
「戦争は、何の罪も憎しみもない他国の人間を敵と称して、殺すことの無神経さを植えつけるだけだからね。まあ日本国民はこれにこりて、今後、ぜったいに戦争はしないようにしなければならない、と俺は思っている」
と、私たちにもよく分るように話してくれた。
◇
p171
確かに、戦争中に私たち少国民に植えつけられた教育は、「敵国の人間はみな理由の如何んを問わず殺すことのみが戦争に勝つことだ」と教えられていた。だから鬼畜米英ということばも平気で口からでたのであるが、いま考えてみると、それがいかにぞっとするような、恐ろしいことばであるか、ということを痛感するのである。
だが私は、米兵と接しているうちに、彼らがどうしてこんなに屈託のない陽気な人間であるのかと、不思議でならなかった。平時にはごく普通の人間でやさしい心をもった人たちであり、戦争中でもおそらく、軍律を守りながらも、自由で快活な軍隊生活を送ってきたのであろう。
そのうえ、物質的にも恵まれていたので、軍人勅諭で束縛され、命令とびんたで追いまわされた、悲壮な日本兵とはおのずからちがった、余裕のある兵士が生まれてきたのではなかろうか、と想像することができる。
私は、戦後間もないころの日本国民の姿を、少年期の肉眼と心の目でみることができたことを、まことに幸いなことと思っている。
p172
その当時の日本人が、日本国再建のためにどんなに苦労してきたことか、すいとんや雑炊、さつまいもの蔓などを食べて、生きるためにどんなに耐え抜いてきたことか。いまもなお昨日のことのように鮮やかに思いうかべることができるのである。
私はこうして過してきた少国民時代の体験を、これからの若い世代に語りつたえ、戦争が人類にとっていかに恐ろしいものであるか、また平和というものが、どんなにありがたく大切なものであるか、ということを、あらためて認識してもらいたいと思っている。
あとがき・・・p173
p173
3年ほど前に友人から「15年戦争時代のことについて、何か書いてみないか」とすすめられたことがあった。そのとき書いてみようとは思ったが、生来、私は日記というものを記したことがなかったので、当時の状況を知る資料になるものは皆無にひとしく、記憶以外には何も残っていなかった。だからせっかくすすめられたが、なんとなく機会を逸していた。
ところが、昭和58年の終戦日も間近いある日の午後、五味川純平の『戦争と人間』を読んでいて、突然、書いてみたい衝動にかられたのである。
15年戦争時代のことといっても、この時代の最初のころの私自身のことは、両親から聞かされていた思い出話をたどりながら書き、史実として知られているものについては、関係資料を参考として、記憶を再確認しながら点筆をすすめていった。
p174
その資料には、戦後の講和条約締結の2、3年前に発行された文部省著作『日本の歴史』と、三上次男著『世界史・東洋史編』のほかに、最近発行された、原田勝正編昭和の歴史の別刊『昭和の世相』を参照させてもらった。
私自身、爆撃や機銃の攻撃を直接うけた体験は、数えるほどしかない。しかし戦時下のあの重くるしい、一日とて心の休まることのなかった日々のことや、また財閥と軍閥に属する人間や狂信者のために、日本国民の多くが、その生活をくつがえされたことなどを思い重ねるたびに、今後、このようなことは絶対にくり返してはならない、といつも念願していたことである。
文章そのものもあまり書いたことのない私だったので、まとめるのにかなりの労力と時間を要した。しかし書き出してみると、当時の不快なことも思い出し、感情的な起伏もないではなかったが、むしろ、在りし日の肉親や、遠い日の還らぬ親友のことなど懐かしみながら、たのしく点筆をはこぶことができた。そして点筆からテープに吹き込む、という作業をすすめていった。
p175
このたびの私の拙い文章を、そのテープから普通文字に書き直す仕事や、また編集と校正に、多大なるご尽力をいただいた、妻の友人である棚田良子さんと、田中千鶴子さんに、心から感謝申し上げる。なお、印刷の諸事についてご配慮賜った、落合典子さんと、東洋出版株式会社社長石井俊夫氏に、厚くお礼を申し上げ、点筆を置かせていただく。
大嶋康夫
昭和59年初夏
年譜・・・p176
p176
昭和 6年(1931) 3月 埼玉県秩父郡秩父町に生まれる
昭和16年(1941) 2月 昭和7年よりこの年2月までに3回、白内障の手術をうけ、両眼視力0.2を得る
昭和19年(1944) 3月 国民学校初等科卒業時、右腓骨骨髄炎発病
昭和22年(1947)10月 ペニシリン注射併用による骨髄炎外科手術
昭和23年(1948)10月 眼球内出血にて完全失明
昭和26年(1951) 4月 埼玉県立盲学校へ編入
昭和35年(1960) 3月 東京教育大学教育学部、特設教員養成部卒業
昭和35年(1960) 4月 静岡県立沼津盲学校、理療科教諭として着任
昭和39年(1964) 3月 藤田陽子と結婚
昭和55年(1980)11月 心筋梗塞による冠状動脈バイパス手術
昭和59年(1984) 現在 埼玉県立盲学校・理療科教諭として在職中
長男 昭彦 19歳、二男 邦彦 15歳
少国民と呼ばれたあのころ
発行 昭和59年8月15日
著者:大嶋康夫
〒350 川越市宮元町58-15
電話 049(223)0703
印刷:東洋出版印刷株式会社
〒112 東京都文京区小石川2-17-3
電話 03(813)7311~4
-終わり-